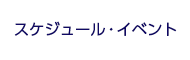オスロ会議に向けての提言集
被爆者の賠償に対する権利と核軍縮
明治大学講師 山田 寿則
はじめに
2010年、NPT締約国会議はその最終文書で「核兵器のいかなる使用も壊滅的な人道的帰結をもたらすことに深い懸念を表明し、すべての国家が国際人道法を含む適用可能な国際法をあらゆる時点において遵守する必要があることを再確認」した。この認識は、その後の国連総会諸決議を通じて、イスラエルを除く他の非NPT当事国も共有するものとなった。同時に、前記最終文書では、締約国会議は「すべての国家が核兵器のない世界を達成しかつ維持するために必要な枠組みを確立する特別の努力を払う必要があることを確認」している(※1)。今日、諸国は、核軍縮を進める過程において、核使用の壊滅的な人道的帰結が存在し、関連する国際法を遵守することを拒否することはできない。同時に「核兵器のない世界」の達成・維持に「必要な枠組み」においては、核使用の非人道性と関連国際法の遵守が的確に位置づけられなければならない。
核兵器の使用がもたらす壊滅的な人道的帰結の最も中心的なものの1つとして、核使用の犠牲者(被爆者)の存在がある。核兵器の使用により壊滅的な人道的帰結が生じることは、ヒロシマ・ナガサキへの原爆投下が実証している。1945年の2つの原子爆弾は、「軍関係者を除いて広島市においては少くとも死者七万人以上、負傷者五万人以上、長崎市においては死者二万人以上、負傷者四万人以上を出すに至った」(下田事件判決)。広島と長崎に投下された原子爆弾のエネルギーは、それぞれ16キロトンと21キロトンTNT火薬に相当するとされている。2013年現在における世界全体の全核兵器のもつエネルギーは広島・長崎での原爆をはるかに超えている。このオスロ会議では、今日の世界に存在する核兵器使用の帰結をヒロシマ・ナガサキの経験に照らして正確に認識することが、なによりもまず重要である。
被爆者の賠償に対する権利の手がかり
それと同時にこの被爆者の救済は、「国際人道法を含む適用可能な国際法」における要請になりつつあることにも注目しなければならない。この被爆者の救済に関連する国際法については、ヒロシマ・ナガサキ以降、見過ごすことのできない発展が生じている。
今から50年前の1963年12月7日に日本の東京地方裁判所が下した判決、いわゆる下田事件判決では、原爆投下を国際法違反と認定していながら、ヒロシマ・ナガサキの被爆者による日本国政府に対する損賠償請求は退けられている。その主な理由は以下の点にある。①個人は常に国際法上の権利主体となりうるのではなく、国際法上自己の名において権利を主張しうるとともに、義務をおわされる可能性がなければならない。それは具体的に条約により承認された場合に限る。よって、違法な戦闘行為の被害者たる個人は、一般に国際法上損害賠償を請求する途はないこと、②日米両国の国内裁判所では個人の国際法上の請求権の訴求はできないこと(日本については国際法上の主権免除の法理から、米国については米国内法上の主権免責の法理から)、③日米両国の国内裁判所で救済を求めることはできないから、原告が主張する国内法上の請求権も存在を認めがたいこと。以上の点である。ここには、カンサード=トリンダーデ(Cancado Trindade)国際司法裁判所判事が指摘するように、「専ら国家間システムに基づいて理解されうち立てられている国際法秩序の不十分さ」が反映されている(※2)。
しかし、今日の国際法では、被爆者を含む国際人道法・国際人権法の違反による犠牲者個人の権利ないしは救済の必要性が確認されつつある。
第1に、人権侵害の被害者には効果的な救済の権利が認められている。1948年の世界人権宣言第8条は「すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する」と規定し、自由権規約2条3項では「この規約の各締約国は、……この規約において認められる権利又は自由を侵害された者が、公的資格で行動する者によりその侵害が行われた場合にも、効果的な救済措置を受けることを確保すること……を約束する」と規定する。この他、人種差別撤廃条約6条、拷問禁止条約14条、欧州人権条約13条および41条、米州人権条約25条および63条、バンジュール憲章21条2項などで、権利侵害に対する効果的な救済の保障を規定している。
これに加えて、武力紛争時の人権侵害について、種々の人権機関が意見を表明し、その判断が蓄積されてきている。この人権侵害事例には、軍事行動中の国家機関によるものも含まれており、人権諸機関がそれについて判断することにより、事実上、敵対行為に関する法規についての判断を蓄積することにつながっている(※3)。
第2に、国連諸機関が、国際人道法上の個人の権利の存在についてのコンセンサスの形成を支持してきている。例えば、2005年には国連総会が「国際人権法および国際人道法の重大な違反の被害者のための救済と賠償の権利に関する基本原則と指針」を採択した(※4)。この原則と指針は、既存の法的義務を確認するものであるが、その名称とは異なり、文書の構成が国家の義務を機軸にすえたものになっており、被害者の権利が中心となってはない。しかし、被害者に対する救済の義務が国家にあることを確認していることは重要である(※5)。
また、国際司法裁判所は、占領地におけるイスラエルによる壁の建設が問題となったいわゆる壁事件勧告的意見においては、「関係するすべての自然人および法人に対して及ぼされた損害を賠償する義務がイスラエルにある」ことを認め、加害国に課された賠償義務を明らかにした(※6)。
第3に、90年代以降、武力紛争後に被害者個人に対する補償を目的とする国際的な委員会が設置されてきている。例えば、1991年の湾岸戦争後に安保理が設置した「国連補償委員会」、旧ユーゴ内戦終結のデイトン合意で設置された「避難民および難民の不動産請求権に関する委員会」、1999年のコソボ紛争に伴い設置された「家屋および財産に関する請求委員会」、2000年エリトリア・エチオピア和平協定によって設置された「エリトリア・エチオピア請求権委員会」、2003年のイラク戦争後に設置された「イラク財産請求権委員会」などである。それぞれに相違点はあるものの、いずれも武力紛争や抑圧体制における弾圧などに起因する国際法違反を理由として、個人がその損害の補償または原状回復を要求する権利をもつことを前提としている。また、国際刑事裁判所の下でも、被害者に対する補償を実現する制度も整備されており、これも個人の補償を受ける権利を前提としている(※7)。
第4に、国内裁判所ではこれまで、個人による賠償請求の試みに対しては国家主権を擁護する立場が強かったが、これにも変化が見られる。例えば、2011年7月5日のオランダのハーグ控訴院判決では、1995年のスレブレニツァでの虐殺におけるムスリム人3名の死亡についてオランダ政府の賠償を支払う責任が判示された(※8)。
第5に、国際人道法違反の被害者の賠償に対する権利を認めるソフト・ロー文書が作成されていることも注目される。例えば、国際法協会(ILA)は、2003年に「戦争犠牲者の補償に関する委員会」を設置し作業を開始し、2010年のハーグ大会では「武力紛争の被害者に対する賠償に関する国際法原則に関する宣言(実体的論点)」を採択した。現在、賠償権の手続的側面に関する検討が進められている(※9)。
最後に、軍縮法の諸条約においても、被害者救済に関連する規定が次第に充実する傾向にある。1993年の化学兵器禁止条約では、国家に対する援助の規定がおかれるにとどまっていたが(10条)、1997年の対人地雷禁止条約では被害者の治療等に明示的に言及した援助規定が置かれ(6条)、2008年のクラスター弾に関する条約にいたっては、独立した条文として被害者に対する援助が規定されている(5条)。同条約の成立については、2006年の障害者の権利に関する条約が影響している(※10)。
このような国際法上の諸実行は、被爆者の救済が法的に要請されていること、ないしは被爆者には賠償に対する国際法上の権利が認められることを強く示唆している。
おわりに
もちろん、課題も多い。とくに、これらの諸実行から、被爆者の権利が現行法として一般国際法上確立しているかどうかについては、厳密な学問的検討が必要だろう。また、被爆者の賠償権を実現するに際しても、将来のありうべき被爆者のみならず過去の(そして生存している)被爆者に対してどのような救済を考えるかについても検討が必要だろう。
しかし、今後核兵器を使用しようとする者は、すくなくとも将来のありうべき被爆者の救済を無視することはできず、そのための負担を覚悟しなければならないことは明らかである。その負担を回避する方途は、核兵器の不使用であることは論をまたない。
加えて、「再発防止の保証」が被害者に対する賠償の一様態として確立しつつあることにも注目したい(前述の2005年の「原則と指針」原則23および2010年IlA宣言10条)。これは、再び核兵器を使用しないとの約束が、被爆者の救済にあたるということを意味している。これは現在の被爆者の主張にも一致するだけでなく、この様態での賠償の実現は、NPT6条の核軍縮義務の実施を別の側面から促進することなる。
このように被爆者の賠償に対する権利の確立は、核軍縮を促進させるものものであって、「核兵器のない世界」の維持・達成に「必要な枠組み」に不可欠な要素となるものなのである。
(※1) See The Final Document of the 2010 NPT Review Conference, Conclusions and recommendations for follow-on actions, NPT/CONF.2010/50 (Vol. I), pp. 19-20.
(※2) See Antonio Augusto Cancado Trindade, International Law for Humankind, Nijhoff, 2010, p.427.
(※3) See Giulla Pinzauti, "Good Time for a Change: Recognizing Individuals' Rights under the Rules of International Humanitarian Law on the Conduct of Hostilities", in Realizing Utopia
The Future of International Law, Antonio Cassese ed., OUP, 2012, pp. 575-576.
(※4) General Assembly Resolution 60/147, adopted on 16 December 2005, UNDoc. A/RES/60/147.
(※5) この「原則と指針」については、以下参照。古谷修一「国際人道法違反と被害者に対する補償」ジュリスト、1299号、2005年;申惠●(ホウ)「国際人権法および人道法の違反に対する責任と救済一一国際人道法の重大な違反の被害者が救済を受ける権利の承認をめぐって」坂元茂樹編『国際立法の最前線』有信堂、2009年;栢木めぐみ「戦争犠牲者の事後的救済―被害者救済のガイドラインを事例として」浦田一郎他著『立憲平和主義と憲法理論』法律文化社、2010年。
(※6) See Legal Consequences cf the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory,
Advisory Opinion, I. C. J. Reports 2004, p. 198, paras. 152-153.
(※7) 古谷、前掲論文(註5)、64頁以下参照。
(※8) English translation of the Ruling of July, 5, 2011 of the Court of Appeal in The Hague in the Srebrenica case, is available at <http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Gerechtshoven/Den-Haag/Nieuws/Pages/RulingofJuly,5,2011intheSrebrenica-case.aspx>.
(※9) 同委員会の文書については以下から参照できる。<http://www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/1018>
(※10) 内海旬子「クラスター爆弾禁止条約における犠牲者支援」社会科学研究、29巻2号、85頁以下参照。