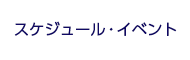〈特別企画〉韓国・原爆国際民衆法廷第2次国際討論会 報告資料
核兵器使用の犯罪性に関する考察
明治大学兼任講師/公益財団法人政治経済研究所主任研究員
山田 寿則
◆はじめに
核兵器の使用は犯罪(国際犯罪)である、という主張は、国際社会ではその最初の使用直後から提起されている。米国による広島への原爆投下後の1945年8月10日に、大日本帝国政府は米国に対して抗議文を発出し、このなかで原爆投下を「人類文化に対する新たなる罪状」と呼んだ(※1)。米国務省の記録ではこの箇所は‟a new crime against humanity and civilization”と記載されている(※2)。この犯罪との言及が、個人犯罪を意味するか国家犯罪を意味するかはかならずしも明らかではないが、「人道に対する罪」(a crime against humanity)として核兵器使用を指摘する最初期のものといえる。
よく知られるように、国連総会の第1号決議は、核兵器の除去等についての計画を策定する原子力委員会の設置決議であった。最初期の原子力委員会からの軍縮交渉25年を通しては、核兵器使用禁止のアイデアはほとんどつねにソ連の提案に基づき全面軍縮か部分的措置として討議されてきた(※3)。
1960年代に入ると核兵器の犯罪性に言及する総会決議が提起されるようになる。
まず、1961年には核兵器の使用が違法であるのみならず、「人類及び文明に対する犯罪」(a crime against mankind and civilization)とした国連総会決議1653が採択された。この決議は、エチオピアなど途上国12ヵ国が提案したものであり、米英等の反対を受けつつも、採択された。その後、現在に至るまで国連総会では、この決議1653を参照する決議が繰り返し採択されている。この核兵器使用(ないしは威嚇)の犯罪性を主張するのは、非同盟諸国あるいはグローバルサウスの国々であり、国連においては、核兵器の使用を犯罪とみなすのは多数派であると言っていい。
しかし、国際法上、核兵器の使用そのものを禁止しても、犯罪とする条約規定はない。(以下、TPNW)でも、核兵器の使用や使用するとの威嚇は禁止されているが、犯罪とはされていない(1条)。交渉過程では、核兵器の使用を犯罪であると言及する国もあったが、それでも核兵器使用を犯罪とする規定はおかれていない。なお、条約の国内実施については、「立法上、行政上その他のあらゆる適当な措置(罰則を設けることを含む。)をとる」ことが義務付けられている(5条)。アイルランドは、これに従って、核兵器禁止法という国内法を制定し、核兵器の使用等を犯罪としているが、すべての締約国が、このように核兵器使用行為そのものをカテゴリカルに犯罪とする法令を制定しているわけではない(なお、核兵器を使用した者が既存の法令により処罰されうることはありうる)。
1998年の国際刑事裁判所(ICC)規程の交渉過程では、核兵器の使用を明示的に国際法において犯罪とすることが議論された。核兵器使用をICCの対象犯罪にするかについて激しい議論の結果、核兵器使用それ自体は、戦争犯罪とされなかった。この議論の影響で他の大量破壊兵器(WMD)についてもその使用は対象犯罪とされなかった(※4)。焦点は、核兵器の使用が「包括的な禁止の対象」となっているかどうかにあった。
ICC規程は、その後、侵略犯罪などが追加されるなど注目すべき改正が行われているが、核兵器の使用は追加されていない。メキシコは2009年から核兵器の使用を犯罪とする改正を提案している。TPNW成立以降は、TPNW等の批准数の推移を考慮する姿勢を見せて、後の討議に付すと発言しているが、提案そのものは撤回していない。
◆核兵器使用の犯罪性を論じる意義
では、このような現状において、核兵器の使用を国際刑事法の観点から検討する意義はどこにあるだろうか。第1に執行手続の存在、第2に犯罪化のもたらす非正当化の効果が指摘できる。
第1に、国際刑事裁判所(ICC)の設立により、一定の国際犯罪については犯罪の行為者を訴追・処罰する手続が整備されてきた。もちろん、ICCの管轄権や犯罪人の引渡し等の点で限界は存在するが、現実にICCのもとで犯罪者が裁かれている事実は重要である。
核兵器の使用が、ICCの対象犯罪(コア・クライム)のいずれかに該当する場合、その核兵器を使用した者がICCの手続を通して訴追・処罰される可能性が生じている。
なお、近年では、国際司法裁判所(ICJ)においても1948年ジェノサイド条約の適用が争われており、この点でも、核兵器の使用がジェノサイド条約に違反する場合には、ICJを通じて使用国の国家責任が追及されうることになる。
第2に、ICCの対象犯罪は、「国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪」に限定されている(ICC規程5条1)。就中、ジェノサイドは、「文明世界から強く非難された国際法上の犯罪」(1946年国連総会決議96(I))とされ、現在では、ジェノサイドの禁止は国際社会の強行規範であることが確立している。仮に核兵器の使用がコア・クライムに該当することが明らかとなれば、その実行者の処罰が可能であるかどうかを超えて、核兵器の使用は国際社会全体の利益を害するものであるとの位置付けが明確となり、その使用の正当性が問われることになる。
これは、核兵器の使用という犯罪への抑止効果が期待できるだけではない。TPNWの締約国は、核兵器の非正当化を目指すとしており、核兵器使用の犯罪性を検討することは、かかる観点からも重要である。
詳細かつ厳密に検討する必要があるが、ジェノサイド条約及びICC規程のもとでは、核兵器の使用は、そのすべてではないにしろ、ジェノサイド罪、人道に対する罪または戦争犯罪に該当する場合があると思われる。また、その場合、その使用を決定した国家指導者個人の刑事責任も追及しうる。
◆おわりにかえて:若干の考察
これに関して、いくつかの点を指摘しておきたい。
第1に、ICCについて言えば、その管轄権の行使には一定の限界があることには注意が必要である。まず、ICCの対象犯罪は出訴期限の対象とならないが(29条)、ICCの時間的管轄(ratione temporis)は、規程発効後に行われる犯罪に限定される(11条)。次に、人的管轄(ratione personae)は、行為地に関係なく締約国の国民に及ぶ(12条2(b))。これに関連して、英仏という核保有国やドイツ、イタリア、ベルギー、オランダといった核共有国、日本や韓国、オーストラリアといった核傘下国が締約国である点が注目される。また、場所的管轄(ratione loci)は、被疑者国籍に関係なく、ICC締約国の領域で行われた犯罪に及ぶ(12条2(a))。現在、ICC締約国は、124ヵ国(パレスチナ国を含む。なおウクライナは未批准国だが、ICCの管轄権を受諾する宣言を出している。)であり、これらの領域内で核兵器が使用された場合は、被疑者の国籍に関係なく、ICCは管轄権を持つ。なお、国連安保理が事態をICCに付託する場合には、ICCの管轄はICC非締約国国民や領域にも及ぶ。
これらの制限内においてICCは核兵器の使用について管轄権を有するが、被疑者の身柄を確保するには、引渡しに関する措置が別途必要となる。また、ICCは、当該犯罪に管轄権を有する国が被疑者の捜査または訴追を真に行う意思または能力がないときに、国内裁判所に代わって管轄権を行使する(補完性の原則)。
第2に、仏英によるICC規程への「留保」の問題である。両国は、それぞれICC加盟国となる際に、ICC規程の適用から核兵器の使用を除外する旨の宣言を出している。他の加盟国からこの「留保」を名指しした異議は申し立てられていないから、この留保は許容されているようにも見える。だが、確かに、ICC規程起草過程では、核兵器使用は犯罪とされなかったが、それはまだ包括的な禁止の対象となっていないとされたからである。ICC規程の対象犯罪は、どの手段であっても成立する。核兵器という手段では成立しないという見解はICC規程交渉過程では支持されていない(※5)。また、仏英の「留保」文書は、それぞれ「解釈宣言」と「宣言」とされており、留保として提示されていない。ICC規程、特に対象犯罪に関する解釈は最終的にはICC自身に委ねられている。
第3に、ジェノサイド条約では、同条約上の紛争はICJに一方的に付託されうる(9条)。注目すべきは、近年のICJは、当事国間対世義務(obligation erga omnes partes)の存在を認めてきており、ジェノサイド条約がかかる義務を定めていると判示したことである(※6)。
ジェノサイドに該当する核兵器の使用について、ICJにおいてジェノサイド条約の他のすべての締約国が違反国の責任を追及することができる。ジェノサイド条約の締約国は9核保有国を含め153ヵ国であり、同条約9条については中国、インド、米国が留保しているが、DPRK、フランス、イスラエル、パキスタン、ロシア、英国は留保を付していない。
また、同条約ではジェノサイドを「国際法上の犯罪」と位置付け、その防止・処罰を締約国に義務付けている(1条)。ジェノサイドの定義については2条で定められているが、同条約では、処罰すべき行為は、この2条で定義されるジェノサイドにとどまらず、その共同謀議、直接かつ公然たる扇動、未遂及び共犯も含まれている(3条)。また、ICJの解釈によれば、同条約は国家自身がジェノサイドを行わない義務を含んでおり、国家がジェノサイド又は3条の行為を行った場合には国家責任が生じる(※7)。
前述したような核兵器使用がジェノサイドに該当するとすれば、その共同謀議等についても、不処罰を理由に、あるいはそのような行為が国家機関によって行われていることを理由に、他の締約国がICJに提訴できる可能性が生じている。
もっとも、ジェノサイド条約は脱退可能な条約である(14条)。同条約を根拠とした訴訟可能性が高まるにつれ、対象となる国の脱退可能性が高まることがあるかもしれない。現実の訴訟を検討する際には留意すべき点である。
いずれにせよ、国家指導者たちが、その発言を通して核兵器の使用を匂わせている。その政治的・軍事的、あるいは人道から見た意義を論じることは重要だろう。だが、法律家には、冷静にその法的意義とその帰結を検討する作業が課せられている。
- 外務省編纂『日本外交文書 太平洋戦争第3冊』外務省、平成22年、1690頁以下、また、朝日新聞1945年8月11日付参照
- United States Department of State, Foreign relations of the United States : diplomatic papers, 1945. The British Commonwealth, the Far East Volume VI (1945), Japan, pp.472-473.
- The United Nations and Disarmament 1945-1970, pp. 152-161.
- 村瀬信也・洪恵子『国際刑事裁判所 第2版』東信堂、2014年、166頁以下参照。
- 真山全「核兵器使用と戦争犯罪-国際刑事裁判所における処罰可能性」『レクナ ポリシーペーパー 核兵器問題の主な論点整理:国際人道法編(2023年5月)REC-PP-18』105頁以下参照。
- ICJ Report 2022, paras. 106-14.
- ICJ Reports 1996, p. 616, para. 32