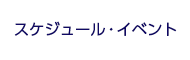(法律文化社、2011年)

著者の藤田久一(関西大学名誉教授、元東京大学教授)は国際人道法の権威として広く知られる国際法学者である。本書は、碩学たる著者の核問題に関する研究の集大成として長く参照されていくであろうことは疑いなく、核問題を国際法の観点から考えるにあたっての最重要文献であると断言できる。
本書の目的は核兵器「使用」の原点から慎重に国際法的検討を加えることにある。なぜ核兵器の使用なのか。著者によれば、オバマ米大統領のプラハ演説以降、核兵器全廃についての明るい見通しが語られているものの、いわゆる「対テロ戦争」をめぐる状況など昨今の国際情勢に照らせば、必ずしも核廃絶への道程が加速しているとはいえず、むしろ核兵器のより使いやすい状況さえ現出しているとされる。このような状況下において、核軍縮(条約)とともにあるいはそのための前提として検討すべきは、核兵器使用の規制ないし禁止の問題であると著者は説く。この目的のため、本書では核兵器の使用規制に焦点を絞り、最初の戦時使用から冷戦期以降の核戦略まで、これに対応する人道法による核兵器使用・威嚇の規制の展開と問題状況が検証されていくことになる。
本書は過去に発表された著者の関連論文を歴史的展開に沿って再編集した全4章および補論から構成され、これに今後の動向ないし検討課題を述べた「むすび部分」が新たに書き下ろされている。各章の内容は編集上の補正を除けば初出論文とほぼ同一であるが、注記が大幅に削除されており、より詳細な理解を得るためには初出論文に当たる必要があると思われる。以上を踏まえ、簡単ながら各章の内容を紹介していこう。
「第Ⅰ章 広島・長崎原爆と国際法―原爆判決を手がかりに」では、核兵器使用に関する問題の原点として、広島・長崎の原爆投下の合法性についての唯一の司法判断である原爆(下田)判決を素材に、当時の国際法の観点からの再検討がなされる。著者は、下田判決の特殊性や限界を指摘しつつも、抽象的議論の投げ合いから抜け出すためにまずなすべきことは、唯一の使用例である広島・長崎の原爆投下を振り返って検討することであると強調する。特に判決の法的権威としての価値を支える国際法学者の鑑定書・判決後になされた論評、さらに判決で触れられなかった違法性阻却事由や刑事法の観点にまで踏み込んだ詳細な分析は二読三読の価値がある。
「第Ⅱ章 核兵器と国際人道法―1977年追加議定書の適用問題」では、冷戦期の人道法の展開における核兵器の位置づけを、ジュネーブ諸条約の第一追加議定書において明文の禁止規定が設けられなかったいわゆる「核兵器ぬき」の状況分析を通して明らかにする。著者は、第一追加議定書の「核兵器ぬき」は当該文書の核兵器不適用を意味するものではなく、むしろ人道法の目的と核戦争とは矛盾するものであると結論づけ、にもかかわらず「核兵器ぬき」が行われてきた背景として、核兵器の位置づけとしての核戦略・核抑止との密接な関係性を指摘している。
「第Ⅲ章 冷戦(平和共存)期における核兵器先制不使用と国際法」では、核戦争の危機が叫ばれた冷戦期の状況の中で、国連の内外で示されてきた核兵器先制不使用の提案についての法的評価が試みられる。核兵器先制不使用という一種の政治宣伝とも見られる提案について、著者は、核問題の重要性に鑑みれば、現代国際法の原則に照らして法的評価を受けることは避けえないのであり、一定の法的意味をもった国家の行態とみなすことができるとして、国際法の観点からアプローチしうる問題であることを強調する。このような認識の下、本章では武力行使禁止原則、および人道法と軍縮法の観点から検討が行われ、先制不使用の提案が積極的に評価される。
「第Ⅳ章 核の脅威に取組む国際司法裁判所―核抑止と自衛の議論」では、核兵器の使用・威嚇の合法性に関する国際司法裁判所(ICJ)勧告的意見について、核抑止と自衛の観点からの論評がなされる。著者は、ICJ意見では下田判決には無かった「自衛の場合」が取り上げられており、その背景には国際政治ないし軍事戦略の理論としての核抑止の問題が伏在していると見るが、これに対するアプローチ方法として、従来、国際政治・戦略と法、特に国際法との関連については、本格的な研究があまりなされてこなかったことを認めつつも、ICJ意見が核抑止政策を自衛権という法概念を通して「法化」(法的フォーミュラ化)しようとしたと枠づけた上で、核兵器を「法の土俵」に乗せて分析を試みる。ICJ意見を契機として、核抑止と関連づけて自衛と核兵器の関係を取り扱いうることを提示する本章は、「核抑止と国際法」という主題を考える際により重要性を帯びてくるものである。
「補論 核抑止論と集団的自衛条約―安保条約体制50年の軌跡」では、人類の生き残りにとって緊急に必要なのは全面的核軍縮であり、そのための条約作りであるとの認識の下、これを阻む核抑止と日米安保体制の展開の文脈において、概括的な検討がなされる。本章では、核抑止論の展開から始まり、日米安保体制および核不拡散条約(NPT)体制と核抑止論との関係、さらに冷戦後の核抑止の状況が論じられる。その上で、最後の切札として核抑止に依存する安保体制が強化されることは、全面完全核軍縮の実現と紛争の平和的解決の促進を阻害する要因ともなっているとの批判がなされる。
「むすびに代えて―21世紀における核禁止の構図:核テロと反テロ核戦争、違法から犯罪へ」では、今日の核兵器使用禁止の問題状況についての著者の見立てが述べられる。著者は、冷戦終結以降、核兵器使用禁止の問題は、一方で、核抑止の効かないいわゆる「ならず者国家」に対して、特に「テロとの戦い」の状況において核兵器(先制)使用の敷居が低くなっており、他方で、核兵器使用を違法のみならず重大な戦争犯罪とみなそうとする国際刑事法の発展、および国際世論の中に使用禁止条約締結を求める動きが高まっているという、相反する状況にあると見る。ここでは、前者の要因により核兵器使用の正当化がなされることに警鐘を鳴らしつつも、後者の状況、特に国際刑事裁判所(ICC)の設立を核兵器の使用禁止と積極的に関連づけることが示唆されている。そして、核兵器使用の全面禁止文書の採択、さらには完全核軍縮条約交渉の完結のためにも、広島・長崎原爆の「原点」からの検証が不可欠であることが再度強調されている。
核兵器の使用・威嚇の違法性を研究者が導き出すのに際し、最も困難な障壁となるのは、その使用例が限られている中で、再び実際に使用される以前に、その違法性を支える理論が確立されなければならないことにある。この難題に正面から取り組む国際法学者がほんの一握りであることは、初歩的な文献調査の時点で十分に思い知らされることになる。これに対し、著者は、人道法の幅広い知見を基礎に、あくまで法解釈論に軸足を置きつつも、実証的な立場からは見放されがちな核抑止の問題にまで怯むことなく踏み込んだ検証を試みている。
読者は、著者がその半生を通して核兵器使用を規制する法的な議論に道筋をつけたことに気づかされることだろう。著者の核廃絶への願いも含め、本書にまとめられた研究成果は、学術的な枠に止まらず「核に立ち向かう」反核コミュニティにも受け継がれていかなくてはならないものといえよう。
初出・機関誌「反核法律家」77号(2013年10月)