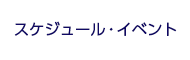機関誌・出版物
被爆国としての道義的義務、核兵器廃絶に向け具体的措置を講ずべき時
明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科
瀬上拡史
核兵器競争は国家の自滅行為と同義であり、二度と再びヒロシマ・ナガサキへの米軍による原爆投下が生み出したような惨禍を起こさぬため、核兵器完全廃絶への努力を積み重ねることは人類の共通の利益である。放射能の充満した黒い雨水が原爆のキノコ雲から無差別に被爆者に降り注ぎ、汚染された空気、水、食物を体内に取り入れることで持続的な内部被ばくが誘発され、原爆症は現在も被爆者とその子孫を苦しめている(※1)。我々は放射能の充満した雨水を凌ぐための傘を求めるであろうが、それは「核の傘」ではない。自国の利益にのみ専念し他国の利益を無下にすれば人類の生存を脅威にさらす。国際紛争は、核保有国が核実験を繰り返し、核兵器開発の継続による抑止力の増大では解決されえない。現存する核兵器備蓄を漸進的に廃棄し、その使用を法的拘束力に基づき全面禁止しなければならない。そして、今後核兵器の増加を防止するためにも核実験を全面的に禁じ、拡散を防ぐための国際的な条約やそれに基づく国内法による規制が求められる。そして、近年影響力を増すNGOを主体とする市民社会が同一の目的の下に国家や国際機関と協働し、人類は核兵器完全廃絶への不可逆的な道を進まねばなるまい。瀬上拡史
莫大な公的資金と技術、天然資源を投じて繰り広げられる核兵器開発競争は一国の経済を停滞させる。外的な脅威に対して核兵器を使用し、先制攻撃をすれば直ちに応酬が始まる。もし核兵器を使用した場合、直接的に被爆をせずとも、当該被爆国の隣接国家群は放射能による環境汚染とともに国民の基本的人権に対する各種の回復困難な損害を与えることは必至であり、経済的にも関係諸国は甚大な被害を受け、相互依存性が深化する現代国際経済を著しく停滞させる。対立する両国共に予測可能な壊滅的被害とその非人道性を核保有国は認識し、その結果を回避するため効果的措置を講じることが将来世代に対する現代に生きる我々の道義的義務である。核兵器完全廃絶の実現のため可及的速やかに全ての核保有国が既存の、そしてこれから形成される条約や国内法を遵守し、核競争の相互不安を払拭するため相互に検証しなければならず、外交努力を怠り将来的に予期し得た結末を迎えることとなれば、それは国家の国民に対する重大な過失と言わざるを得ない。
2020年の核兵器拡散防止条約(NPT)再検討会議に向けて核兵器廃絶に向けた議論が深まりを見せている。日本へと原爆が投下されてから74年が経過した。日本国憲法第9条第一項は戦争放棄を規定し、第二項では戦力不保持と共に交戦権を否定する。しかし、戦後から今日に至るまで日米安全保障条約により米国の保有する強大な核兵器の抑止力の中に蹲る日本を自覚せざるを得ず、日米地位協定及び、在日米軍駐留経費負担に係る特別協定を根拠に拠出される「思いやり予算」として2016年度から2020年度までに9465億円もの負担額が計上されている(※2)。国家の正当防衛としての個別的自衛権、そして集団的自衛権の行使に対して、憲法九条は国家の自衛措置という名に隠された暴力性の増大をくい止める最後の砦となりえるのか。現在の核兵器の威力は、開発と実験が重ねられた結果、米国が広島と長崎に投下した当時の原爆の破壊力の数百倍から数千倍の威力のものまで開発することが可能となった。ローレンス・リバモア国立研究所が2019年5月に臨界前核実験により核備蓄の安全性向上を報告したが、核兵器の持つ非人道性、不正義、無秩序、そして使用された場合の公共の利益への回復不可能な著しい損害を再認識し、日本はそれらを甘受するわけにはいかない(※3)。核兵器の使用または威嚇による抑止力に基づく支配ではなく、憲法第九条やNPTを理念だけではなく実質面でも堅持し、「法の支配」に基づき核兵器完全廃絶に向けて積極的外交努力を重ねなければならない。
NPTは非核兵器国の核兵器の製造や備蓄を禁じ、工業分野、原子力発電、医療分野などの核エネルギーの平和目的利用を促進する基盤となっている。核技術が人類文明の壊滅か発展かどちらのために利用されるかは、人類自身の選択に委ねられた。その選択は後述するオタワ条約やオスロ条約におけるNGOの活躍にみられるように、条約成立過程におけるNGO等の行動が織りなす国際世論に大きく影響を受けるため、我々一人一人の市民の弛まぬ行動は政策形成に向けた原動力となる。核軍縮へのプロセスと核備蓄の大幅削減に向けて2020年のNPTの再検討とさらなる草の根の取り組みが求められている。NPTは第6条において「各締約国は、核軍備競争の早期の停止及び核軍備の縮小に関する効果的な措置につき、並びに厳重かつ効果的な国際管理の下における全面的かつ完全な軍備縮小に関する条約について、誠実に交渉を行うことを約束する」と規定する。2010年に赤十字国際委員会が告発した核兵器の「非人道的結末」(※4)は、その「法的禁止及び廃棄」へと帰結せねばならず、その法的な間隙を橋渡しするため、第6条に規定する効果的な諸措置の具体的な内容を迅速に規定し、法的拘束力を有する枠組みの中で履行しなければならない。具体的には、核実験の禁止、核兵器の削減、役割低減、検証の実施、透明性向上、不可逆性の確保など、多様な措置を包含し、核軍縮義務を効果的措置に具現化し、迅速に履行することが求められる。核技術は非人道兵器開発のために利用されるべきではなく、日本国憲法の理念に基づき、条約や国内法により厳正に規制し、その使用は平和目的利用に限定されなければならない。
NPTに加えて、包括的な核実験禁止条約は核兵器の開発と製造、拡散を防止する抑止力となり、核兵器軍備競争を停滞させる要因となる。核実験により生ずる放射能に汚染された降下物への懸念から、1963年に部分的核実験停止条約(PTBP)が締結された。1996年には包括的核実験禁止条約(CTBT)が採択され、いかなる大気、水中、地表、地下、宇宙空間などの環境における、あらゆる種類の実験的爆発及び他の核爆発、核実験を禁止した。しかし、本条約の付属書IIにおいて記載される発効要件国である44か国の内、中国や北朝鮮、インド、アメリカ合衆国等が批准していないため、2019年現在も本条約は効力を有していない。米国はCTBTを批准しないまま核兵器開発を継続し、一方では北朝鮮に完全で不可逆的な非核化を迫るなど、説得力のある姿勢とは到底言えない。国際安全保障体制下での核の抑止力としての機能の増大も指摘される中、「核の役割」を減衰させる努力が核開発競争に歯止めをかける。核兵器の抑止力としての役割の増大と、核兵器廃絶への希望、国際社会は天秤のどちらに比重を傾けるのか。
2019年2月、米国はネバダ州で臨界前核実験を成功させた。この実験は核備蓄の安全性を向上させたというが、あらゆる条件下においても核実験を禁じた包括的核実験禁止条約の精神に違反し、核兵器廃絶に向けた国際社会の動向と逆行している。ローレンス・リバモア国立研究所は2003年にネバダ実験場の地下実験施設で最初の臨界前核実験を実行し、備蓄安全性向上のための科学的方法を発見したと報告している。備蓄の安全性が向上することは核兵器の安全性を保障するものではなく、核兵器が存在する限り、その安全性の向上など本質的にはありえないと再確認しなければならない。平和目的利用の実験であるとはいえ、新たな核兵器開発や性能維持及び改善という目的を内包することは自明である。エディザ(Ediza)(※5)を含む五年に及ぶ実験の成功は、本来回避すべき潜在的な核軍備競争を助長する要因となりえないか。地下実験による核備蓄の安全性の向上は、核の効用、核兵器の存在の重要性を増大させ、核保有の正当化を試みるだろう。1986年の絶頂期から、核備蓄は国際的に減少傾向にあり、この傾向を逆行させてはならない。CTBTが禁ずる核爆発を伴わないとはいえ、臨界前核実験の成功による核備蓄の安全性の向上を喧伝し、核保有の正当化根拠とするようなことがあってはならない。核兵器の効用の減衰に向けた法的な取り組み策定に向け、米国を含め核兵器保有国は如何なる条件下でも核実験を行わないことを包括的核実験禁止条約の下に再検討しなければならない。
核兵器禁止条約の第1条1項は、「締約国は,いかなる場合にも核兵器その他の核爆発装置を開発し,実験し,生産し,製造し,その他の方法によって取得し,占有し,又は貯蔵することができない」と規定する。そして、限定的な自衛措置としての使用、また抑止力としての使用の可能性も排除すべきものとする。冷戦期に米国とソ連の間で生じたような緊急の危難、国家の存亡が関わるような安全保障上の危機が生じた場合でも、また再び米国と北朝鮮の緊張関係が極度の高まりを見せたとしても、核兵器の限定的な使用も許容されない。しかし、国際司法裁判所(ICJ)は、「国家の存亡に関わる自衛の極限的な状況」においては核兵器の使用が合法か違法か「判断できない」と指摘する。国家生存がかかる場面における「自衛」としての核兵器使用の権利の許容性については、核兵器使用以外に自国の存立を保持する手段がないとしても、核兵器使用の違法性は阻却されず、使用は許容されないと主張したい。均衡性の原則により、自衛行為としての核兵器使用は相手国からの武力攻撃に対してあまりに均衡を欠き、また自衛という目的を果たすための核兵器使用という手段に相当性を認めることは到底できない。1975年の万国国際法学会(※6)において強国と弱国の武力不均衡を弱国が超克するために核兵器使用を許容すべきかとの問題提起に対しても、多数見解は強国も核兵器で反撃するに至り、核ホロコーストが生じる現実的危険が存するとして、自衛という目的を終局的には果たすことはできないとして、核兵器の使用を許容しない。つまり、本質的には如何なる条件下でも使用を禁じられるべきこの非人道兵器は国際紛争を解決するための抑止力にさえなりえないのである。核の傘から離脱するとき、それは日本の核武装への要請には直結しない。「目には目を、武力には武力を、そして核兵器には核兵器を」、という恐怖に囚われた先入観から離脱し、不毛な核拡大競争に歯止めをかけ、積極的平和外交による多国間安全保障を創造すべきである。
積極的平和外交は非核兵器地帯のより広範な地域への拡大を目指すべきである。南極大陸やラテンアメリカ大陸における非核兵器地帯の形成を先例として、積極的交渉により非核兵器地帯を可能な限り最大の地理的範囲に拡大し、核兵器完全廃絶への不可逆的な道を進まねばなるまい。特に、「北東アジア非核兵器地帯」(※7)の創設を構想するにあたり、朝鮮半島の歴史と情勢への公正な認識に基づく対応が求められる。1953年に朝鮮戦争の休戦協定が締結されるものの、戦時中も協定締結後も北朝鮮は米国による核兵器使用の脅威に晒され続けている。米国からの威嚇に対応し自国の存立を保持するために核兵器開発と保有の必要性に直面したのである。韓国との関係においては1992年に南北非核化共同宣言が発行し、原子力エネルギーを平和目的利用に限定することや、核兵器の実験、製造、貯蔵、配備、及び使用を禁止すること等が約された。しかし、日本や韓国が米国の「核の傘」の中にあり、核抑止力政策に依存している政治的条件下では、北朝鮮が歴史的に戦時中から現在に至るまで逃れることのできない懸念を払拭することはないであろう。非核兵器地帯形成には関係諸国の歴史的かつ政治的条件を個別に認識する必要があり、先ずもって核抑止力依存政策から脱却し、NPT第六条が規定する義務に基づき核兵器廃絶に向けた効果的措置を講ずる中で、相互信頼を醸成するための法的枠組みの形成と遵守が求められている。
国際紛争は市民の生命、身体、財産などを含め、基本的人権と人間の安全保障への回復困難な危害を加える。国家や国際機関に加え、我々一人一人の市民と、市民が組織するNGO(非政府組織)の協治により安全保障政策を形成する必要がある。1996年4月、核廃絶の可能性を検討するため、INESAP(拡散に反対する国際科学技術者ネットワーク)、IALANA(国際反核法律家協会)、IPPNW(核戦争防止国際医師会議)等三つの国際NGOが協働し、「モデル核兵器禁止条約」を制作し、これがコスタリカやマレーシア政府の主導により国連の審議に付され核兵器禁止条約が検討されるに至った。国連憲章第71条の理念のもとに、経済社会理事会は市民社会における第三セクターとして、軍縮など特定分野において専門知識や経験を有するNGOと協議している。非政府の非営利団体は経済社会理事会との協議資格を取得することで国連との間で相互利益的な協働体制を構築する。この資格に基づき2012年時点で3,735のNGOが理事会と同一の趣旨の下に協働できるパートナーとしての地位にある。国際人権法の枠組み内で活動する条約の履行状況について条約参加国政府だけではなく、NGOも独自に条約履行状況を条約機関に対して提供することで条約機関はより公正な判断を下せるようになる。多くの反核団体が指摘してきたように、非核三原則の法制化に向け、NGOを含め市民社会が今後も国際的な世論の形成主体とならなければならず、NGOに実質的な力を付与するのは我々一人一人の市民の善意であることを認識して行動を重ねるべきである。
政府、国際機関、ネットワーク化するNGOの協働による条約締結への過程は非核三原則の法制化に向けた取り組みにも活かされるはずである。対人地雷の禁止条約制定の際に、対人地雷の非人道性を最初に各国政府に告発し、国際世論を喚起し、法的拘束力を有する対人地雷禁止条約(オタワ条約)の締結へと導いたのは、1992年に欧米のNGOが中心となり設立した地雷禁止国際キャンペーン(ICBL)である。その後オタワ条約の条約成立プロセスを模範として、クラスター爆弾を禁止するためのクラスター爆弾禁止条約(オスロ条約)が交渉開始から1年3か月という短期間で締結された(※8)。ジュネーブ条約第一追加議定書には「戦闘員と民間人を区別する」「不必要な苦痛を与えてはならない」という二つの原則が提示されている。対人地雷やクラスター爆弾は、国際人道法としてのこれら二つの原則に違反するとして、多くのNGOがその報告書により非人道的被害の実態を訴えることで使用禁止に向けた国際世論は高まりを見せ、法的拘束力を有する国際法制定の必要性が叫ばれた。米露など大国が反対する中、NGOの報告に呼応するように、ノルウェー政府などが禁止に向けて積極的に動き出し、有志国を主体とする中堅国家群が先導し、国際世論の高まりを活かし、国際機関やNGOとの協働により新たな条約制定を実現した。対人地雷及びクラスター爆弾禁止条約に向けてイニシアチブをとり続けていたのはネットワーク化したNGOの連合体であり、これらは有益な情報源として市民社会を啓蒙し、安全保障政策に影響を与えてきたのである。
核の傘の柄を握りしめながら核兵器廃絶を声高に唱道する矛盾に満ちた日本を、日本の市民はただ漫然と眺めているのではない。核兵器禁止条約締結に向けて現状に悲観的にならず、核戦争防止国際医師会議(IPPNW)から派生して2007年に設立されたICAN(核兵器廃絶国際キャンペーン)がノーベル平和賞を受賞するなど積極的で建設的な努力を成功事例としてNGO活動をより広範囲に拡大してゆかなければならない。ICANは2015年のNPT再検討会議においても核兵器禁止条約の国際的なキャンペーンを展開し、国際NGOである中堅国家構想を主軸とした新アジェンダ連合との連携が2000年NPT再検討会議における「核兵器廃絶の明確な約束」に対する合意形成においても貢献した。また、政府の主体である国会議員との連携を形成し、民意を法政策において効率的に反映してゆく手段として、中堅国家構想のイニシアチブに基づき2001年に「核軍縮・不拡散議員連盟(PNND)」が結成された。これに日本の国会議員も参加し、核政策に関する世論を個別具体的な現実の法政策に活かし、核兵器完全廃絶への不可逆的な道程を進まなければならない。国際世論形成におけるこれらのNGOの広範な活動は、NGOと政府、そして国際機関とのさらに強固な連携を訴求するものである。NGOを含めて市民運動の活性化を促進することは民主主義の名の下に民意を反映した安全保障政策の実現に資する。
国際司法裁判所は国際人道法の基礎となる人道の基本的考慮に核兵器が適合しないと指摘する。ICJの勧告的意見は核兵器使用や核兵器による威嚇は「一般的に国際人道法に違反する」と1996年に指摘した。東京地方裁判所が1963年に下した原爆判決(※9)の中で、米軍のヒロシマ・ナガサキへの原爆投下は、文民と戦闘員を区別しない「無差別爆撃」である点、そして「不必要な苦痛」を生じさせてはならないとする点の二点を要件とし、上記二つの観点から国際法に照らして違法性を認定した。核兵器不拡散条約締結から50年を迎えた今、ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)によると、核兵器は2019年1月時点で約1万3800個余り存在すると推計されている。74年前に投下された原爆の被害は投下直後だけではなく、今尚持続的に被爆した人々の体質に影響を与え、白内障や複数種類の癌、癌以外にも原爆症として多くの疾病の原因となっている。核兵器全面廃絶への人類の訴求は、核兵器という大量破壊兵器の持つ非人道性に由来し、国際司法裁判所が指摘するように、既存の国際法に照らせばその違法性は明白である。核兵器完全廃絶と恒久的な国際安全保障体制の確立のため、可及的速やかに法の支配を確立し、核兵器を廃絶するための直接的かつ具体的な措置を講じなければならない。核兵器完全廃絶こそ人類の真の安全保障体制の確立を意味し、それは弛まぬ努力により堅持されなければならない。決して第二の被爆国を生み出さぬよう、核兵器が恒久的に使用されないことを保障する唯一の方法は、その全面廃棄にしかありえない。
1 キノコ雲の中には核兵器の残骸や塵等の放射性物質が含まれている。「黒い雨」は重油のような粘り気のあるような大粒の雨で、放射性降下物(フォールアウト)の一種。この雨に直接打たれたことによる二次的な被爆が原因となり頭髪の脱毛や、歯茎からの大量の出血、血便、急性白血病による吐血など急性放射線障害を罹患した。
2 在日米軍の駐留経費における日本側の負担のうち、人件費や訓練移転費などの一部を日本が負担する。日米両政府は2016年度から2020年度の期間で9465億円を拠出する旨を定めた特別協定に合意。2021年3月末に協定は期限を迎えるため、日米交渉は新協定締結に向け本格化する見通し。
3 核爆発直前の核物質の物理的反応を調べる実験。核物質を臨界状態に至らない条件に設定して行う核実験。臨界に達する直前の状態,つまり核爆発を起こすことなく核爆弾の性能を測定する実験であり、環境への影響はないとされる。
4 赤十字国際委員会が核兵器の「非人道的結末」について2010年に報告した。Statement by the President Jacob Kellenberger, “Bringing the era of nuclear weapons to an end,”International Committee of the Red Cross, 20 April 2010.
5 「エディザ」とは西部ネバダ州の核実験場でアメリカ・エネルギー省が所管するローレンス・リバモア国立研究所が2月13日に実施した臨界前核実験である。プルトニウムを反応させるために高性能爆薬を使用し、核分裂の際のデータを測定。この実験により、保有する核弾頭の安全性向上につながったと評価する。
6 万国国際法学会(Institut de Droit International(IDI))は、ヨーロッパなどから11人の国際弁護士が1873年にベルギーにおいて設立された。国際法の研究と発展への貢献を目的とした組織であり、人権や幸福追求権に関わる法改正も促進した功績から1904年度のノーベル平和賞を受賞した。
7 日本と韓国と北朝鮮の3カ国を核兵器の開発や保有を禁じる地帯にする構想である。そして、核保有国の中国、ロシア、米国は上記参加国に対して核攻撃しないと約束するアプローチが有力。非核兵器地帯の条約は以下の5地帯で既に成立している。北東アジア非核兵器地帯創設については、梅林宏道氏の提唱する「スリー・プラス・スリー」案や、ジョン・エンディコット氏の提唱する非核兵器国が「限定的非核兵器地帯」を創設する構想などがある。(『非核兵器地帯 核なき世界への道筋』, 146-156)
8 クラスター弾、集束爆弾とも呼ばれる。クラスター爆弾の不発弾の非人道性について、「意図的に不発になるよう仕組まれ、復旧作業を妨害する」「子供を含め民間人の興味を引く形状をしており、拾うように仕向けている」「地雷禁止条約の抜け道として、不発弾を地雷代わりにしている」とし、非人道的であるといった批判があがる。クラスター爆弾の廃絶を目指すNGOの国際的連合体であるクラスター爆弾連合は、2011年にはICBLと合併し、クラスター爆弾禁止条約の成立にノルウェー政府と連携し条約成立に貢献した。
9 下田判決とも呼ばれ国際的にも注目された。サンフランシスコ講和条約によって日本国が国民の損害賠償請求権を放棄したため、対米賠償請求が不可能となり、これに対して日本政府は、原爆被害者に補償・賠償すべきであるという趣旨の裁判である。判決は原告の請求を棄却したが、原爆投下は、確立した軍事目標主義の原則に反し、さらに非人道的兵器の禁止の原則にも違反するとした。日本国内の裁判所による原爆投下の違法性を認定した世界で初めての判決である。
【参考文献】
1. 土山秀夫「九条はよらば大樹の陰なのか」『論文集 核廃絶への道』長崎文献社名,2011年7月1日,p.86
2. 「包括的核実験禁止条約(CTBT:Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty)」外務省ホームページ (最終閲覧日:2019年9月15日)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kaku/ctbt/gaiyo.html
3. CTBTO Preparatory Commission, Status Of Signature And Ratification(最終閲覧日:2019年9月1 日)
https://www.ctbto.org/the-treaty/status-of-signature-and-ratification/
4. ローレンス・リバモア国立研究所(Lawrence Livermore National Laboratory、LLNL)ホームページ(最終閲覧日:2019年9月1 日)
https://www.llnl.gov/
5. 「米国 臨界前核実験、2月実施 17年12月以来」『毎日新聞』, 2019年5月25日 東京夕刊
https://mainichi.jp/articles/20190525/dde/007/030/032000c
6. 富塚明「米国が5年ぶりの未臨界核実験 後退する透明性 」『核兵器・核実験モニター 軍事力に頼らない安全保障体制の構築を目指して』ピースデポ, 2018年11月1日, 555号, p.7
http://www.peacedepot.org/wp-content/uploads/2018/10/nmtr555.pdf
7. 藤田久一『核に立ち向かう国際法』法律文化社, 1-9, 186-195 2011年10月10日
8. 梅林宏道『非核兵器地帯 核なき世界への道筋』岩波書店,123-131, 146-156, 2011年9月28日
9. 国際連合広報センター, 非政府組織(NGO)との関係
https://www.unic.or.jp/info/un/un_organization/ecosoc/ngo/
10. Statement by the President Jacob Kellenberger, “Bringing the era of nuclear weapons to an end,” International Committee of the Red Cross, 20 April 2010.
11. 目加田説子『行動する市民が世界を変えた クラスター爆弾禁止運動とグローバルNGOパワー』毎日新聞社,2009.10 ,p.26-p.56
12. 土山秀夫「いま、核廃絶のために何をなすべきか」『論文集 核廃絶への道』長崎文献社名,2011年7月1日,p.147
13. 鈴木達治郎, 光岡華子, 『こんなに恐ろしい核兵器 ②核兵器のない世界へ』ゆまに書房2019年1月30日, p.18
14. 大久保賢一, 日本反核法律家協会ホームページ,「核兵器使用の非人道性と原爆投下の違法性
―原爆裁判・下田判決50年記念シンポのご案内―」 2013年11月18日 (最終閲覧日2019年9月1日)
http://www.hankaku-j.org/data/04/131118.html
15. 大久保賢一, 日本反核法律家協会ホームページ, 「原爆投下は国際法に違反するとの判決を想起しよう」2013年7月1日 (最終閲覧日2019年9月1日)
http://www.hankaku-j.org/data/04/130701.html
16. Norwegian People’s Aid, Colin King, the Norwegian Defense Research Establishment, M85:An Analysis of reliability, issue report, December 2007.
17. Handicap International, Circle of Impact: The Fital Footprint of Cluster Munitions on People and Communities, Brussels, May 2007, p23(Cambodia)
18. International Campaign to Ban Landmines, Landmine Monitor Report 1999
19. UNOCHA,“A lasting legacy: the deadly impact of cluster bombs in Southern Lebanon,”OCHA Report, 19 September 2006
20. Human Rights Wa