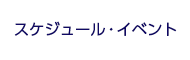松井芳郎
はじめに
1963年12月7日、東京地方裁判所は広島・長崎への原爆投下は国際法に違反するとの判決(以下、原爆判決という)を下した。これは、広島・長崎で被爆した下田隆一氏をはじめとする5名の原告が、原爆投下の違法性を前提として、損害賠償を求めて提訴した裁判である(国際的には「シモダ・ケース」として知られる)。裁判所は、損害賠償請求は退けたものの、当時の実定国際法規の原則に照らして原爆投下は違法であったと判断した。
この論考では、原爆判決をその後の国際法の発展―とりわけ、保護法益が交戦者の平等の確保を目的とする「戦争法」から、戦争犠牲者個人の保護に着目する「国際人道法」へと発展を遂げたこと―の中に位置づけて、その歴史的意義を検証する。
Ⅰ 「原爆判決」評価のポイント
1.核兵器使用の国際法的評価の基本的な論点の提示
原爆判決は広島・長崎への原爆投下の国際法上の合法性について判断したものであって、国際的にも核兵器の使用に関する初の司法判断である。論点は大きく分けて明文の禁止がない新兵器の使用について国際法の適用があるかどうかという点と、原爆投下は、戦争法の2つの基本原則、すなわち軍事目標主義(「区別原則」)と不必要な苦痛を与える兵器の使用禁止とに依拠して違法といえるかという2点である。
1996年のICJ核兵器の威嚇・使用の勧告的意見(以下、勧告的意見という)が以上の論点を踏襲していることをみても、判決の歴史的意義は、広島・長崎への原爆投下という具体的な事例を越えて、核兵器の使用一般に適用可能な国際法の論理を提示したことにあるといえよう。
また、核廃絶のアプローチとして近年とみに注目されるようになった核兵器の非人道性についてこの判決がどのように判断したのかについても触れておきたい。
2.核兵器使用への国際法の適用の確認:「新兵器への不適用」論の否定
新兵器の登場の段階ではこれを特定的に禁止する慣習法はもちろん、条約も存在しない。また、国際法上特定的に禁止されていない兵器の使用は許されるという伝統的主張は根強く存在し、核兵器についても主張される。
原爆判決は、この論点について、「19世紀後半以後の関連諸条約は新兵器である原爆の投下について直接には禁止規定を設けていないが、こうした禁止にはその旨の明文がある場合だけでなく、既存の国際法(慣習国際法と条約)の解釈及び類推適用からして、当然禁止されているとみられる場合を含むと考えられる。さらに、それらの実定国際法の基礎となっている国際法の諸原則に照らしてみて、これに反するものと認められる場合をも含むと解さなければならない。国際法の解釈も、国内法におけると同様に、単に文理解釈だけに限定されるいわれはない。」と判断している。
判決は既存の慣習法と条約の解釈及び類推適用、ならびにそれらの基礎にある国際法の諸原則を適用できるとしたのである。
3.戦争法の2原則からの評価
(1)軍事目標主義(「区別原則」)
判決は、「国際法上戦闘行為について一般に承認されている慣習法」によれば、陸海軍による砲撃に関しては防守都市と無防守都市が区別されており、空襲に関しては、1923年の「空戦に関する規則案」が「陸戦及び海戦における原則と共通している点から見ても、慣習国際法であるといって妨げない」と判断してこれを援用し、広島と長崎は、防衛施設や軍隊が存在しても戦場から遠く離れ敵の占領の危険が迫っていない無防守都市であったことは「公知の事実である」から、「原子爆弾による爆撃が仮に軍事目標のみをその攻撃の目的としたとしても、原子爆弾の巨大な破壊力から盲目爆撃と同様な結果を生ずるものである以上、広島、長崎両市に対する原子爆弾による爆撃は、無防守都市に対する無差別爆撃として、当時の国際法からみて、違法な戦闘行為であると解するのが相当である」と判示する。
このように判決は、明文の関連条約規定が存在しないこの争点については、軍事目標主義という戦争法の基本原則に依拠して判断した。その後1977年のジュネーブ諸条約第Ⅰ追加議定書が、防守都市と無防守都市の区別を廃止して軍事目標主義=区別原則を全面的に適用したことに鑑みれば、本判決が国際人道法の発展に大いに寄与していると評価できよう。
(2)不必要な苦痛を与える兵器の禁止
次いで判決は、不必要な苦痛を定義する1868年のサンクト・ペテルブルグ宣言や不必要な苦痛を与える兵器等の使用禁止を規定するハーグ陸戦規則第23条eを援用して、広島・長崎への原爆投下により「多数の市民の生命が失われ、生き残った者でも、放射線の影響により18年後の現在においてすら、生命をおびやかされている者のある〔という〕悲しむべき現実」に照らして、「原子爆弾のもたらす苦痛は、毒、毒ガス以上のものといっても過言ではなく、このような残虐な爆弾を投下した行為は、不必要な苦痛を与えてはならないという戦争法の基本原則に違反している」と述べる。この論点を提起したことも原爆判決の重要な意義といえよう。
4.評価の基準としての非人道性
原爆判決が広島・長崎への原爆投下行為を国際法違反と断じた背景には、原爆の非人道性、残虐性についての認識が存在した。判決は広島・長崎における被爆の実相について直接の事実認定を行っていないものの、「原子爆弾は従来のあらゆる兵器と異なる特質を有するものであり、まさに残虐な兵器であるといわなければならない」と結論するに当たって、原爆に特徴的な放射線から生じる「各様の身体障害の恐ろしさは、既にわれわれが見聞しているところである」と述べている。判決は、日本においては公知の事実に属する被爆の惨害をふまえて原爆の非人道性を結論したのである。
Ⅱ 国際人道法の発展と核兵器の使用
1.「戦争法」から「国際人道法」へ:保護法益の転換
1968年世界人権宣言20周年を記念して開かれたテヘラン国際会議の決議XXIII「武力紛争における人権」を受けて、国連総会が「武力紛争における人権の尊重」を議題に取り上げ、ジュネーブ諸条約1977年第Ⅰ追加議定書の採択に至る国際人道法の立法過程が始まる。
国際人道法は、国連憲章で武力行使が禁止された下では、侵略者と侵略の犠牲者との平等の確保という法益には疑問が生じるが、犠牲者個人の保護という法益は引き続き維持されている。
さらに、近時、国際人権法と国際人道法の相互浸透ともいうべき現象が見られるようになり、人権諸条約上の保護は、特別な場合を除いて武力紛争時においても停止しないとみなされるようになった。核兵器の使用への人道法の適用を考えるにあたっては、このような変化を念頭に置かなければならない。
2.ジュネーブ諸条約1977年第Ⅰ追加議定書と核兵器の使用
(1)区別原則(軍事目標主義)の徹底:第48~58条
第Ⅰ追加議定書は、「文民たる住民それ自体及び個々の文民は、攻撃の対象としてはならない」(第51条2);「攻撃は、厳格に軍事目標に対するものに限定する」(第52条2)と規定し、無差別攻撃を無条件に禁止した(第51条4)。原爆判決が依拠した伝統的戦争法における防守都市、無防守都市の概念は放棄され、軍事目標主義、すなわち区別原則をすべての場合に適用するという立場である。
禁止される無差別攻撃を定義する第51条4並びに文民保護強化を意図する第54条、第56条などを合わせて考えると、議定書の下で核兵器の使用が合法的である余地はまったくない。
(2)不必要な苦痛を与える兵器の禁止の再確認:第35条;第36条
議定書は、第35条2において不必要な苦痛を与える兵器の禁止を再確認している。この規定は一般原則であって、特定的禁止のない核兵器の使用には適用されないのだろうか。しかし、一般原則と適用範囲を定める議定書第1条2がマルテンス条項、すなわち「文民及び戦闘員は、この議定書その他の国際取極がその対象としていない場合においても、確立された慣習、人道の諸原則及び公共の良心に由来する国際法の諸原則に基づく保護並びにこのような国際法の諸原則の支配の下に置かれる」を定めている。したがって、議定書第35条1及び2が規定する不必要な苦痛を与える兵器の禁止は、その第1条2に定めるマルテンス条項と合わせて読むならば、核兵器の使用にも適用されるものであることは明らかである。
(3)自然環境の保護:第35条3;第55条
議定書は、自然環境保護の要素を導入した。すなわち第35条3は「自然環境に対して広範、長期的かつ深刻な損害を与えることを目的とするまたは与えることが予測される」戦闘の方法及び手段を用いることの禁止を、第55条1は戦闘においては自然環境をそのような損害から保護するために注意を払う義務、またその損害から住民の健康や生存を害することを目的とするまたは与えることが予測される戦闘方法及び手段の使用の禁止を、それぞれ規定している。これらの条文が想定する環境損害は、通常兵器によるものではなく、核兵器などの大量破壊兵器によるものであることを強く示唆する内容である。
3.戦争犯罪としての核兵器使用:国際刑事裁判所ローマ規程第8条2(b)(xx)
核兵器の使用は人道に対する犯罪を構成しあるいは戦争犯罪であるという主張を実施に移す仕組みは長年にわたって存在しなかったが、国際刑事裁判所(ICC)ローマ規程が2002年に発効したことによって、そのような可能性に道が開かれた。このローマ規程第8条2(b)(xx)「武力紛争に関する国際法に違反して、その性質上過度の傷害もしくは無用の苦痛を与え、または本質的に無差別な兵器、投射物及び物質並びに戦闘の方法を用いること」は、第Ⅰ追加議定書第35条2を受けたもので、明記こそしないが核兵器の使用を想定した規定と読むことができる。
かつては運動論のレベルで核使用が戦争犯罪であると主張されていたことが、現在では実定法たるローマ規程の解釈のレベルで論じられるようになった事実は、明らかに議論の進展を示している。
Ⅲ 国際司法裁判所「核兵器の威嚇または使用の合法性」勧告的意見
1.意見の枠組み
国連総会は、「核兵器の威嚇または使用は、いずれかの状況において国際法により許容されているか?」についてICJに勧告的意見を求めた。ICJは主文(1)で勧告的意見の要請に応じることを決定し、主文(2)で合法・違法を検討にしている。
裁判所は、主文(2)A及至Dで、核兵器の威嚇または使用に関する特定的な許可は存在しないこと、及びそれに関する包括的かつ普遍的な禁止も存在しないことを確認し、国連憲章第2条4に違反し第51条の要件を満たさなければ、使用兵器を問わずすべての兵器において武力の行使またはその威嚇は違法であり、抑止により核を保有することが憲章第2条4の「威嚇」に該当するかどうかは想定されている武力行使が同条によって禁止されているかどうか、また自衛目的ならば必要性と均衡性の原則に反するかどうかにかかると述べた。
核兵器それ自体の威嚇または使用を特定的に禁止する条約上の規則または慣習規則は存在しないと認定した裁判所は、それが国際人道法の原則及び規則に照らして違法かどうかに論を進め、主文(2)Eで「核兵器の威嚇または使用は武力紛争に適用される国際法の規則、及びとりわけ人道法の原則ならびに規則に、一般的には違反するであろう。しかしながら、(中略)国の生存そのものがかかっているような自衛の極端な状況において核兵器の威嚇または使用が合法であるか違法であるかについて、裁判所は確定的に結論することができない」と判示したのである。
ここで裁判所は、違法かどうかの判断基準とすべき国際人道法の基本原則として、第1に無差別攻撃を禁ずる区別原則、第2に不必要な苦痛を与える兵器を禁ずる原則を挙げる。そのうえで、裁判所はマルテンス条項に言及し、それは軍事技術の急速な発展に対応するために有効な手段であることを証明されたという。裁判所はまた、人道法の諸規則の大部分は人間個人の尊重と「人道の基本的考慮」にとってきわめて基本的なものであり、「国際慣習法の犯すことができない諸原則を構成するから、これらを規定する諸条約を批准したかどうかを問わずすべての国によって遵守されるべきものである」と述べ、国際人道法の基本原則が慣習法としてすべての国を拘束するということを認めるものである。
このように人道法の基本原則を核兵器に適用するにあたり、裁判所が「核兵器の独自の特徴」、すなわちその非人道性について克明な認定を行っている事実と、国際人道法の「本質的に人道的な性格」を繰り返して強調していたことには、注目しておく必要があろう。
2.勧告的意見の評価―国際人道法の2原則から
(1)核兵器の人道法上の評価:意見主文(2)E前段
しかしながら、裁判所自身が核兵器の非人道性を認めておきながら、その使用については人道法の基本原則を適用した結果「一般的には違反するであろう」といった、例外が存在するような言い方になることは理解しがたい。しかも、裁判所はこの点での具体的理由づけを与えていない。核使用が区別原則の禁ずる無差別攻撃に該当し、核兵器が不必要な苦痛を与える兵器以外の何ものでもないことは明らかである。にもかかわらず、理由づけを与えなかったのは、このような不可避的な結論を避けて「例外」の抜け道を開き、紙一重で裁判官の賛成多数を確保するための苦肉の策だったのだろう。
それでは、どのような「例外」がありうるのか。意見が引用した唯一の可能性は、英・米の主張した、公海上の軍艦や人口希薄な地域の部隊に対する爆発力が低い核兵器の使用は文民への副次的被害が少ないという点だった。しかし、これでは区別原則への例外とはなり得ても、不必要な苦痛を与える兵器の使用禁止の例外とはならない。まして問題なのは、自ら「既存の慣習法の表現」と評価したマルテンス条項に目をつぶって、不必要な苦痛を与える兵器禁止の基本原則の核兵器への適用可能性について、具体的な検討をいっさい行わなかった点である。
(2)自衛権論:意見主文(2)E後段
勧告的意見が「例外」となりうる可能性として示唆したのは、「国家の存続それ自体がかかっているような自衛の極端な状況」だった。しかしながら、ある武力行使が自衛の要件を満たすかどうかは、国連憲章や自衛の法に照らして正当化できるかどうかの判断のレベルの問題で、これをクリアすると判断されたときに、次に武力紛争法に照らして兵器の性質や使用方法に違反がないかが検討されることになる。したがって、自衛の要件を満たすことが、人道法の基本原則に違反する戦闘の手段・方法の違法性を阻却する理由とはならない。ここで裁判所は大きな論理的矛盾を犯しているのである。
3.核軍縮交渉を誠実に行いかつ完了させる義務:意見主文(2)F
最後に裁判所は、「F.厳格かつ実効的な国際管理の下における全面核軍縮に向けての交渉を、誠実に実施し及び完結させる義務が存在する」と述べる。このF項は国連総会の諮問事項とは対応せず、したがって厳密にいえば裁判所の権限踰越ともいえるが、裁判所がこの判示をもって厳しく対立のあった意見を、最後に全員一致で締めくくったことには、大きな意義があろう。これは、核兵器のような破滅的な兵器の法的地位について見解の相違が継続することは、国際法と国際秩序の安定性とにとって有害だろうと裁判所が考えたからにほかならない。
しかもこの義務は、一見NPT第6条の言い換えのようにも思われるが、これを単なる交渉の義務にとどめず、交渉を誠実に遂行することによって全面核軍縮を達成する義務にまで発展させたこと、かつ、この二重の義務は、NPTの182の締約国にかかわるだけでなく、全面完全軍縮とくに核軍縮の現実的な探求はすべての国の協力を要するものであることを認めた点で、裁判所は既存の議論を一歩進めたといえるだろう。
むすび
原爆判決と勧告的意見とを隔てる30年余りの年月の間に、前者が適用した伝統的な戦争法は、ジュネーブ諸条約1977年追加議定書に象徴されるように国際人道法へと発展した。戦争法が交戦者の平等の確保を主要な保護法益としたのに対して、国際人道法では「人道の基本的考慮」に基づき武力紛争の犠牲者である個人の人権と人道的な待遇を確保することが優越的な保護法益となる。原爆判決はこのような国際法の発展を見事に予言していたといえる。とりわけ、新兵器だった原爆の投下への既存の戦争法の適用を肯定したこと、そして軍事目標主義=区別原則と不必要な苦痛を与える兵器の禁止という戦争法の基本原則に依拠してその合法性について判断したことは、核兵器使用の国際法上の評価を行う際によるべきモデルを示したという意味で、原爆判決の歴史的意義を際立たせる。勧告的意見は、原爆判決を直接引用しているわけではないが、国際的にシモダ・ケースとして知られる原爆判決は英訳され公刊されていて、裁判官は判決文を読んでいるだろうと思われる。勧告的意見は、原爆判決のモデルを大枠として踏襲したのである。
それでは、国際人道法の確立をふまえた勧告的意見は、核兵器の使用禁止と核廃絶に向けて原爆判決の立場をどこまで前進させたのか。先に勧告的意見の問題点を指摘したが、同意見がいくつかの積極面を有することは疑い得ない。勧告的意見は、従来核保有国とその学者の間に根強く存在してきた、新兵器である核兵器の使用については既存の戦争法ないしは人道法は適用されないという議論にとどめを刺した。勧告的意見はまた、核兵器の非人道性を強調するとともに、国際人道法の人道的な性格を際立たせて、核兵器の使用は人道法の原則及び規則と「ほとんど両立しがたい」と認めた。
その勧告的意見のつまずきの石となったのが、自衛権論とその背後にある核抑止論だった。裁判所は、主文で「自衛の極端な状況」における核使用の合法・違法の判断を放棄したのは、相当数の国(an appreciable section)が長年にわたって依拠してきた抑止政策の慣行も無視できないことを理由の一つとした。したがって、核使用の全面的な違法性を確認するためには、核抑止論の克服が不可欠の課題となる。
そして核抑止論の克服のためには、国を単位とする旧来からの軍事的な安全保障観に代えて、個人の平和に生きる権利の確保を目指す新しい安全保障観、「人間の安全保障」観を確立する必要がある。核抑止論は自国の「安全保障」のために相手国の国民全体を人質に取るというもっとも極端な非人間的発想に根差すものであって、この意味で国際人道法の反対概念であるだけでなく「人間の安全保障」の反対概念でもある。
「人間の安全保障」観を確立して核抑止論を克服するには、現実政治を動かす必要がある。そのためには国内外の世論が大きな役割を果たすことを、原爆判決と勧告的意見は示している。原爆判決の背景には、1954年の第五福竜丸事件を契機に盛り上がった原水爆禁止運動があり、ICJに勧告的意見を求める国連総会決議の背後には、国際反核法律家協会(IALANA)をはじめ多くの反核NGOsを傘下に収める「世界法廷プロジェクト」の活動があったことはよく知られている。反核NGOsは、またICJの審理過程においても少なからぬ影響を与え、日本政府と見解を異にする広島と長崎の市長が、極めて異例のことながら日本の口頭陳述に参加したのは、こうした運動の成果だった。
戦争法から国際人道法への発展の背景には常に、戦争の悲惨な体験に基づく市民の間の人道意識の高揚があった。この発展は、おもに市民の間における人道意識の高揚とそれに支えられた運動の力を背景としてもたらされたものである。勧告的意見が確認する「全面核軍縮に向けての交渉を、誠実に実施し及び完結させる義務」は、核兵器国をはじめとする諸国の政府にだけ委ねておいたのでは履行されるはずがない。国連総会で何度も速やかなる核廃絶交渉の開始を求める決議がなされても、いまだ交渉が始まらない事実は、国家間のレベルだけでは進展が期待できないことを示すものである。この困難を打開するのは反核運動に結集する国際世論の力をおいてないであろう。つまりICJは、反核運動が投げかけた課題を反核運動の側にいわば投げ返したのである。今こそ、反核運動の真価が問われている。
(この論考は、2013年12月8日東京で行われた日本反核法律家協会主催『原爆裁判・下田判決50周年記念シンポジウム』における基調講演を事務局の責任で要約したものである。)
初出・機関誌『反核法律家』83(2015春)号
バックナンバー申込フォーム