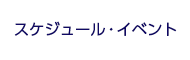弁護士 大久保賢一
はじめに
当協会は、この間、山田寿則さん、山本リリアンさんの協力を得ながら、「新原爆裁判」の可能性と現実性について検討を続けてきた。山田さんには、「米国における国内救済の可能性と限界」、山本さんには「原爆投下を米州人権委員会に持ち込む可能性」をテーマとして研究していただいた。その研究結果はそれぞれ報告書が提出されているので、ぜひそれを参照していただきたい。この報告は、その研究と検討の結果を踏まえての中間総括である。今後の方針を定める上での参考としていただきたい。
1.「新原爆裁判」の意義の確認
「新原爆裁判」は、広島・長崎の被爆者が米国政府を相手取って、公式な機関で法的責任を追及することによって、核兵器廃絶に寄与したいという試みである。ここでの被爆者は日本国民に限るものではないが、核開発、核実験や原発事故のヒバクシャは含まれていない。公式な機関とは、米国の連邦裁判所と米州人権委員会(米州人権裁判所ではない)が想定されている。他の公的機関も検討したが、適切と思われる機関は見出せなかった。法的責任追及とは原爆投下の違法性、被爆者への対応の違法性などである。原爆投下の国際人道法、国際人権法違反を想定している。核兵器廃絶に寄与するとは、この裁判だけで核兵器廃絶ができないことは自明であるので、被爆者が米国を相手として法的手段による行動に立ち上がることによって、核兵器廃絶を求める世界の運動に積極的インパクトを提供したいという含意である。
原爆投下という未曾有の犯罪行為の実相(その被害は投下時から現在まで続いている)を基礎におき、その国際法違反を論証して、核兵器の廃絶を求めるという構想である。63年前、米国は被爆者に何をしたのか、その後現在まで被爆者はどのような状況に置かれ、何を求めてきたのか。これらを集大成したい。そして、核兵器の先制使用戦略をとる米国の姿勢を告発し、その姿勢を転換させ、核兵器廃絶への道を拓くことに貢献しようという試みである。この裁判で求めることは、「米国は核兵器を使用してはならない。」、「米国は核兵器を廃棄しなければならない。」である。過去を踏まえた上で、未来を展望する訴えである。
2.米国での裁判の可能性と限界
(1) 被爆者の米国政府に対する訴えは、一般化すれば、戦争被害者が加害国に対して救済を求める裁判である。戦争被害者個人が加害国政府に対して損害賠償を請求する法的根拠があるかどうかは、我が国における戦後補償裁判(下田事件も含む)で繰り返し提起されてきた論点である。ここには二つの論点がある。ひとつは、そもそも個人が国を相手に裁判ができるかという問題であり、もうひとつは個人の請求権を根拠付ける法があるかである。
(2) 米国では「主権免責の法理」が存在している。「主権免責の法理」とは「国王は悪をなさない」という英米法の思想である。単純化していえば、人民は政府が行なった行為について法的責任を追及できない、という考えである。もちろん、民主主義国家において、この思想がそのまま通用することはありえない。現に、米国においても「主権免責」を放棄して、救済措置を可能とする法律も制定されている。連邦不法行為請求権法、外国請求権法、外国人不法行為請求権法などである。しかしこれらの法律は、戦時中の軍隊の戦闘活動に起因する請求については認めていない。被爆者は敵国の人民であり、原爆投下は戦闘活動である。米国の現行法に基づく請求は認められないといわざるを得ない。
(3) ところで、米国憲法修正5条は「・・・法の適正な過程(due process of law)によらずに、生命、自由、財産を奪われることはない。・・・」としている。しかしこの条項が、米国外の被爆者に適用されることは難しい。また、ハーグ条約等の国際人道法に基づく請求も困難である。
(4) 更に、サンフランシスコ講和条約によって、日本国民の米国に対する請求権は、(仮にそれがあったとしても、)放棄されている、とされる可能性は高い。
(5) 手続き的困難さもある。連邦民事訴訟規則は、裁判での法的主張が現行法に基づいていることや、現行法の拡張・修正・廃止などについては誠実な主張であることを要求し、その条件を満たさない場合には訴訟当事者に制裁を課すとしている。この裁判は現行法の拡張、修正、廃止を求める裁判である。米国の弁護士たちが及び腰になるのは無理もないといえよう。
(6) このように米国での裁判は極めて困難であることが検証された。にもかかわらず、この裁判を提起することの意味はどこにあるのかを問わなければならない。核兵器先制使用戦略を採り、使える核兵器の開発を進める米国政府の行動に歯止めを掛け、核兵器使用禁止、核兵器全面廃絶の方向に米国政府の方針を転換することに役立つことになるのか。世界の反核平和運動に貢献することになるのか。それとも、単なる蟷螂の斧でしかなく、むしろ運動に混乱や分裂をもたらすことになるのではないか。真剣な議論が求められている。
3.米州人権委員会への個人請願
(1) 米州機構に米州人権委員会がある。この委員会は、米州人権宣言に根拠を置く機関で、米国もこの人権宣言を承認している。この人権宣言で保障される人権を侵害された個人は、侵害国を相手方として、この人権委員会に救済を求めて「個人請願」をすることが認められている。人権委員会は請願を妥当と認めれば、相手国に対して、必要な処置をとるよう勧告することができる。米国は、米州機構の一員であって、委員会は米国に対する勧告も行っている。(ただし、米国は米州人権条約は認めておらず、したがって、米州人権裁判所の管轄権はない。)この人権委員会に、被爆者が米国政府を相手方として「個人請願」を申し立てようという提案である。請願の趣旨は、米国連邦裁判所への提訴と同様に、「核兵器使用禁止」と「核兵器の廃絶」である。
(2) この委員会への請願が認められるためにクリアーしなければならない問題点がいくつかある。1.原爆投下は、1945年であり、米州人権宣言は1948年である。この条約をさかのぼって適用できるか、という時間的管轄の問題である。2.原爆投下は日本での出来事である。米州機構加盟国以外の出来事に人権委員会の地域的管轄が及ぶかという問題である。3.国内救済の完了という問題がある。人権委員会に請願する前に、米国内での救済手続きを経てこなければならないとされているのである。4.また、仮に請願が認められたとして、その効果はどうなのかという問題もある。以下、順に検討する。
(3) 時間的管轄と「継続的侵害」
原爆投下は1945年8月である。しかしながら、被爆者は、現在も原爆投下による放射線に起因する病気で苦しめられている。被爆者は、原爆投下によって、今なお、「生命、自由、安全」(人権宣言1条)を侵害されているのである。原爆放射線が、現在も、被爆者を苦しめていることは、日本政府も認めていることである。であるがゆえに、日本政府も、不十分ではあるが、被爆者援護を行なっているのである。このことは、原爆投下による被害は、原爆投下時に止まるものではなく、現在も継続していることを意味している。だとすれば、被爆者による請願は、1945年当時の出来事を問うのではなく、現在継続中の人権侵害を問題にすることになるのである。このように理解すれば、時間的管轄の問題はクリアーできるであろう。
(4) 地域的管轄
原爆投下時も、現在も、日本は米州ではない。米州人権宣言の域外適用が認められるのは、米州機構加盟国の「実効的支配」が及ぶ場合とされている。原爆投下時、米国が日本を「実効支配」していたといえるのか、また、降服から占領終結時までの間の米国の支配を問題にすれば足りるのか、などの議論が必要であろう。いずれにしても、この論点は難問である。
(5) 国内救済手続きの完了
米州人権委員会への請願の前に、米国内での救済手続きを経る必要があるとすれば、米国内での救済手続きを取ればよいだけの話である。ただ、そうした場合、米国政府と裁判所が、正面切って対応することはせず、ずるずると手続きを遅らせて実質的な進展がないままに、時間が過ぎてしまうのではないかという恐れが生ずる。その恐れを避けようとすれば、次のような方法がある。米国の現行法によれば、被爆者が米国によって救済される方策はないことを論証して、米国内での手続きを経ないで、人権委員会に請願する方法である。それではインパクトが弱いということにもなりかねない。とにかく、一度、米国の裁判所に裁判を提起して、その対応が救済拒否と同じだとして、人権委員会に請願するというのが、現実的方法のように思われる。
(6) 請願容認の効果
仮に、すべての条件を満たして請願が受理され、米州人権委員会が米国に「核兵器使用の禁止」と「核兵器廃絶」を勧告するようなことがあれば(人権委員会には勧告以上の権限はないし、米国は今まで委員会の勧告的意見に従ったことはない)、米国がそれをどの様に受け止めるかどうかはともかくとして、大きな政治的効果があることは言うまでもないであろう。米国は国際司法裁判所の勧告的意見を無視して、いまだ、核兵器全面軍縮のための誠実な交渉に入ろうとしていない。その米国が、米州機構人権委員会の勧告など無視するであろう、という悲観的議論もありうるが、世界の反核平和勢力を励まし、核兵器廃絶条約に向けての大きなステップになるであろう。
4.今後の課題
「新原爆裁判」の構想は、「被爆者は自分たちで最後にして欲しい。」、「人類と核兵器は共存でない。」「核兵器をなくして欲しい。」との被爆者の思いを受け止め、法的手段によるアプローチを試み、核兵器使用禁止と核兵器廃絶の運動に寄与できないかというものである。その法的手段には様々な困難が伴うことが明らかとなった。これは、現行法は核兵器の前で不十分であり、「力の支配」から「法の支配」への転換を目指すためには、「あるべき法」を「今ある法」にしなければならないということでもある。核兵器廃絶のための法的枠組みは、核兵器廃絶条約の成立である。そのためには、様々な政治的ベクトルがその方向で収斂する必要がある。そのベクトルとして有効に機能する「新原爆裁判」のありようを模索するために更に議論を深めていきたい。