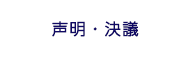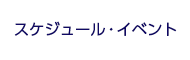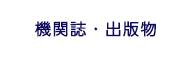中西寛京大教授が、1月15日付毎日新聞朝刊の「核廃絶の理想と現実」と題するコラムで「兵士の視点」も理解を、と主張している。概略以下のとおりである。
兵器は犠牲者にとっては人殺しの道具であるが、兵士にとっては自らと愛する人を守る手段である。核兵器は、平和運動家にとって最悪の非人道的兵器である一方で、軍事戦略家にとってはその脅威によって戦争を回避することを可能にする兵器でもある。核兵器禁止条約に対する日本政府の立場は、まさにこの犠牲者と兵士の視点で引き裂かれている。禁止条約は核兵器廃絶を目指す取り組みであるから、日本政府がこの条約の精神に反対することは困難である。しかし、「兵士の視点」から考えた場合、化学兵器や対人地雷と同列に扱う条約案は現実性を欠くだけではなく、核廃絶にとってもマイナス効果を持つかもしれない。核兵器国は条約に賛成していないから、発効する可能性はないので宣言的文書にしかならない。核抑止は絶対的なものではないが心理的効果を持っており、それは軍事政策全般に及んでいるので、補助的な役割しかない兵器とは根本的に異なる。核兵器だけ取り出して削減する計画は、一定程度進んでも、国際情勢を不安定化するなら大きな揺り戻しをもたらす危険性を持つ。日本人の核廃絶の願いは真摯なものだが、そうであればこそ「兵士の視点」を理解する努力も必要となる。
結局、氏は、核兵器の廃絶はいうけれど、国際環境の現実の中での核兵器の役割を考えれば、核兵器禁止条約は非現実的であるだけではなく、負の役割を果たすことになるとしているのである。核兵器禁止条約の交渉開始に反対している日本政府の姿勢を、「兵士の視点」から理解しようという理屈でサポートしているのである。
こういう論稿を読むのは不愉快だけれど、このような議論を乗り越える論理と運動が求められているのであろう。
氏は、兵器は自身と愛する人を守るものだという。そこには、国家によって戦場に送り出された兵士が、兵士相互の殺傷を強制される戦争という不条理についての視点は全くない。「兵士の視点」をなくすという視点がないのだ。
また、戦闘行為において、無差別兵器や残虐兵器などの使用は禁止されているという国際人道法の視点もない。核兵器は平和活動家にとってだけ非人道的兵器であるのではない。核兵器は、無差別なだけではなく、兵士を残虐に殺傷する兵器でもある。こういう「兵士の視点」も必要なのである。
氏は、日本政府は犠牲者と兵士の視点との間で引き裂かれているという。けれども、引き裂かれてなどいない。政府は、核兵器国と非核兵器国のかけ橋の役割を果たすなどというけれど、核兵器国と歩調を合わせ、条約交渉の開始に反対しているのである。氏の議論は政府の態度を免罪するものである。
氏は、禁止条約は非現実的だとか、無意味だとか、マイナスの役割を果たすなどという。もし、この禁止条約の交渉開始が、国際政治の上でその程度の影響しかないのなら、核兵器国としても放っておけばいいだけの話であろう。けれども、アメリカは、核兵器禁止条約交渉開始決議に反対するよう同盟国に必死に働きかけたのである。アメリカは交渉が開始され、核兵器を違法としその廃絶を求める条約が成立すれば、核兵器の違法性が確立され、その使用のみならず、配備や移転などにも支障がでることを恐れているのである。このように条約交渉の開始決議は、アメリカに大きなインパクトを与えているのである。そのこと自体が、この条約の国際政治に与える影響の大きさを物語っているといえよう。氏の議論は、禁止条約の成立に水をかけようとする姑息なものなのである。
氏は、核抑止は絶対的ではないが、心理的影響はあるとしている。絶対的な抑止力などそもそもあり得ないし、核抑止論は心理的要素に依存する「理論」である。そして、氏は、核兵器は「戦争を回避することを可能にする兵器」であるかのように言っている。氏は、典型的な核抑止論者なのである。核兵器は、自分と愛する人を守るものであることを忘れるな、核兵器禁止条約を急いではならない、とお説教しているのである。私は、このような言説に騙されない。
私は、「兵士の視点」をいうのであれば、核兵器の合理化ではなく、見ず知らずの人を殺傷することを強いられないこと、生まれてきたことを呪うような殺され方をしないこと、戦場の体験をトラウマにしなくて済むことなどを考えることだと思う。
そして、氏には、学問研究の成果を、現実のあれこれの説明や政府擁護ではなく、非人道的で不条理な現実を改革し、核兵器の一日も早い廃絶のために生かすことを期待したい。