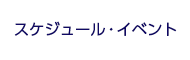情報・資料・意見
国際会議「核世代における人権、将来世代と罪」のご報告
「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟(生業訴訟)弁護団
川崎合同法律事務所
弁護士 中瀬 奈都子
2017年9月14日から17日にかけてスイス・バーゼル大学において開催された「核世代における人権、将来世代と罪」と題された国際会議において、関根未希弁護士(福島市・あぶくま法律事務所)とともに、福島原発事故の被害と訴訟の現状について報告をしてきた。関根先生からは、福島原発事故直後から現在にいたるまでの写真をスライドに投影しながら、被害実態を切々と語っていただき、私からは、私と関根先生が弁護団員として取り組んでいる「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟と賠償の実情について報告した(会議の参加者は、スライドに投影された、事故から時が止まったままの強制避難区域の街並みやその街並みを防護服に身を包んだ裁判官が歩く様子を写した写真など目を丸くしてみていた。)。ここでは、実際の発言内容をもって報告と代えさせていただきたい。川崎合同法律事務所
弁護士 中瀬 奈都子
なお、当該会議の3週間後、福島地裁は、国と東電の法的責任を明確に認め、平穏生活圏侵害による慰謝料について、第一陣訴訟原告3,824名のうち2,907名の請求を認め、中間指針等に基づく賠償対象地域よりも広い地域について賠償対象とし、かつ、既払い賠償金に対する上積みを認める判決を下した。現在は弁護団員一丸となって控訴理由書の作成に取り組んでいる最中である。
最後となったが、共同報告者の関根先生、そして、丁寧なアドバイスとフォローをして下さった山田寿則先生(明治大学兼任講師)、篠原翼さんに感謝を申し上げたい。
(以下、発言内容)
原発事故後、福島にとどまった、あるいは、福島から各地に避難した被害者は、それぞれ、福島あるいは避難先において、国や東京電力を相手に、原発事故でこうむった被害の救済を求める訴訟を提起した。現在、全国各地の約30箇所の裁判所で、合計約1万2千人の被害者がたたかっている。
私と関根弁護士が弁護団員としてかかわっている「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟(以下、「生業訴訟」という。)は、この内、約4,000名を原告として抱える最大の訴訟である。今日は、被害者に対する賠償の実態を踏まえながら、当該訴訟について報告する。
生業訴訟では、居住地の空間線量を、事故前の空間線量である毎時0.04mSv以下にせよという原状回復の請求と、空間線量が毎時0.04mSvに戻るまでの間、月5万円の慰謝料を支払えという損害賠償請求をしている。国と東京電力を被告とし、原発事故発生からちょうど2年の2013年3月11日、福島市にある福島地方裁判所本庁に提訴を行った。
約4,000名の原告は、「原発事故前の地域を、暮らしを取り戻したい!」という根源的要求を実現するため、国や東京電力による被害者の選別と分断を乗り越え、すべての被害者に対する救済を求めること、金銭賠償の実現だけでなく、生活再建策や環境回復策、医療健康管理策などの具体的な制度化を求め、ひいては脱原発社会を実現すること、これら制度形成や政策転換のために、一企業である東京電力だけでなく、国の法的な責任を明確にすること、といった訴訟の目的に賛同し、集まった方たちである。避難者が避難先で提訴する他の訴訟と違い、福島県から避難した人も、県内にとどまった人も原告となっており、また、年齢層も職業等も多種多様である。生業訴訟の原告の被害には、事故被害のほとんどすべての類型が現れている。
原子力紛争審査会が策定した中間指針は、とても不十分かつ、被害者に大きな分断を持ち込んだ。政府が出した避難指示に基づいて避難した人には、月10万円の慰謝料が支払われたが、それ以外の地域に住んでいた人には、ごく少額の慰謝料が支払われたか、あるいは、一切支払われなかったのである。賠償金額の大きな差によって、住民間に意見対立が生じた。
しかし、被害者の分断は加害者にとって思うつぼである。不十分な賠償の枠組みを乗り越え、すべての被害者が一体的にたたかわなければ、国策で今も進められている原発政策を転換させ、「原発事故前の地域を、暮らしを取り戻す」という要求は実現できない。全ての被害者が分断を乗り越えて、国と東京電力の法的な責任を明らかにし、これをテコとして政策を転換・形成していく。これが生業訴訟の大きな意義である。もちろん訴訟だけでは政策転換の目的を実現することはできない。原告団は、結成総会において、訴訟と運動は車の両輪であることを確認し、訴訟と並行して運動を推し進めていくことを確認した。
訴訟において、国や東京電力は、原告らの被害について、「20mSvを大幅に下回る被ばくの健康リスクは、喫煙や野菜不足などの健康リスクと比べても低く、統計上も明らかにできない程度のものだから、法的に権利侵害と評価できない。原告のいう精神的苦痛は、科学的根拠のない危惧・不安のたぐいにすぎない」と主張している。
しかし、原発事故の被害は年間積算線量が20mSvを超える強制避難区域に留まるものではない。たとえば、成元哲教授(中京大・現代社会学部)率いる「福島子ども健康プロジェクト」による、福島県内陸部にある9市町村に事故当時住んでいた、2008年度出生児全員とその母親(保護者)を対象にしたアンケート調査の結果では、事故から3年経過した2014年時点でも、回答者(母親)の6割以上が「健康影響の不安」、「子育ての不安」を抱えており、2~3割が配偶者や両親や周囲との認識のずれを感じていることが明らかになっている。子どもを被ばくさせないために、外遊びを極力避けさせるようにしたり、布団や洗濯物を外に干すことを避けたり、地元産の食材を食べさせることを避けたり、市販の飲料水を購入するなどの生活の変容を余儀なくされた家庭は多く、こういった放射線防護策を巡って祖父母世代と意見対立しているケースは少なくない。
また、原発事故前は、日常的に山に入り、春にはタケノコを、秋にはキノコをとって、あるいは季節を問わず山菜をとって、旬の恵みを享受する「里山の暮らし」があったが、高齢者も含め、放射性物質に汚染された山へ立ち入ることを控える人はどの地域においても未だに多い。日常生活は確実に変容せしめられたままである。
原告は、このような被害実態を立証し、「被ばくの健康リスクについては様々な科学的知見があるが、原告らの被害は、単に健康リスクの増大という点にとどまるものではない。健康リスクを避けるため、避難をしたり、避難をしないまでも、様々な被ばく回避のための行動を余儀なくされ、生活の全てにわたり、様々な生活変化が生じており、そのこと自体が被害である。また、リスク認知心理学の見地からは、原発事故や放射性物質汚染について、一般人が、よりリスクを深刻に受け止める心理が働くのは当然であり、その点からも、被害は現実に存在している」と主張してきた。
訴訟では、このような被害実態を裁判官に深く理解させるべく、約4,000名の中から、35名の「チャンピオン」を選出し、原告本人尋問を行うこととなった。原告本人が、被害を語ることは容易なことではない。それは、自分自身のプライヴェイトな部分をさらけ出すことになるからである。しかし、35名の原告は、自身の被害を、裁判官の前で、国や東京電力の代理人の前で、切々と、堂々と語ってくれた。
また、弁護団は、提訴から2年目の段階から、裁判官3名に法廷の外に出て、被害実態を五感によって体験してもらう「検証」の申立てを行った。そして、申立から約2年経ってようやく、防護服に身を包んだ裁判官3名が、強制避難区域である浪江町、双葉町、富岡町に立ち入った。双葉町では、JR常磐線双葉駅から原告宅まで、時が止まったままの無人の商店街を静かに歩いた。線量計が「ピーピー」と鳴り続け、未だ高線量であることを否応なしに実感させられる中、検証が実施された。
検証が実施されたのは、全国各地で行われている約30件の訴訟の中で初めてのことであったため、大きく報道された。その後、各地の訴訟でも検証実施に向けた動きが出てきているようである。検証期日で、原告らの指示説明を頷きながら真剣にきいていた裁判官の姿に、被害を目の当たりにさせることの重要性を実感した。
一方、原発事故から6年が経過した今、政府主導で、被害隠し・被害者切り捨ての政策が推し進められている。2017年3月末をもって、現在も年間20mSvを超えている地域以外のほぼ全ての地域について、政府による避難指示が解除された。
原発事故から5年以上経過し、ようやくふるさとに戻って良いとされること自体は、喜ばしいことに思えるかもしれない。しかし、政府は、避難指示の解除とともに、2018年3月末で慰謝料月10万円の支払いを打ち切る等の方針を発表したのである。避難指示が2014年4月以降に解除された福島県田村市、川内村、楢葉町、葛尾村、南相馬市の5市町村で、解除された地域への住民の帰還率が全体で約13%にとどまる(2017年1月末時点。なお、事故後住民票を他所へ移して「転居」となった人はカウントされていない)。20mSvという数値は、一般公衆の被ばく線量限度値の20倍もの数値である。その上、より線量の高い地域への避難指示は解除されていないため、地域がまるで切り取られた状態となっており、インフラの整備等も含めて原発事故前の生活環境に戻ったとは言いがたい状況であり、帰還を決断する住民が少ないのは当然である。しかし、慰謝料の支払いが打ち切られれば、線量や生活環境への不安から帰りたくないと考えている人も帰らざるを得ない状況に陥ってしまう。20mSvでの線引きによる賠償の打ち切りで、被害者に対して、事実上帰還を強いるということだ。
また、福島県は、法に基づき、強制避難区域外からの避難者に民間のアパートなどを無償で提供してきたが、2017年3月末をもって、これが打ち切られた。福島県内外に存在する、避難区域外からの避難者は、約3万2000人に上る。先ほど述べたように、避難区域外の住民に対しては、ほぼ賠償がなされていない以上、住宅支援は唯一の支援策だったため、これが打ち切られるのは、避難者に対して打撃的である。
このような政府・福島県の動きは、先ほど述べた訴訟における国や東京電力の主張と合致するものである。つまり、被害者に対し、年間20mSv以下の線量は我慢しなさいという考えを押しつけ、切り捨てようとしているのである。
このような逆風の中、全国に係属している福島原発事故についての被害救済を求める訴訟は、2017年から2018年にかけて、結審や判決を連続的に迎えることとなる。既に3月17日に群馬訴訟で判決が下り、国と東電の法的責任が認められた。次には、千葉への避難者が千葉地裁に提起した訴訟が9月22日に判決(※編註)を迎えることなる。
そして、生業訴訟は、丸4年の審理を経て、2017年3月21日に結審し、10月10日に第一審判決を迎える。この判決では、群馬訴訟、千葉訴訟、生業訴訟の3連続で国と東電の過失責任を認める判決となるか、避難者か滞在者か問わず全ての被害者に現実に被害が生じていることを明確に認める判決になるか、が最大の焦点となる。期待される判決が実現すれば、3連続で裁判所が国と東京電力の事故に関する法的責任を認めることになる。福島県民の大多数が、国や東電に対し賠償その他の要求をする権利を持つことを、国家機関である裁判所が認めたということになる。その政治的意味は極めて大きく、全国のメディアや有識者からも注目されている。
事故の責任や、被害者救済・福島県の復興、また、原発再稼働などをめぐる国民世論に対しても、大きなインパクトを持ちうる判決となる。原告団は、この判決をテコに、経産省等の省庁や福島県との交渉を行い、政策転換を求める運動にまい進する予定を組んでいる。日本における原発事故被害の救済を求める訴訟とその判決内容に注目をしていただければ幸いです。
初出・機関誌「反核法律家」94号(2018年2月)
※編註 千葉地裁判決は、東電に対する請求の一部は認めたものの国の賠償責任を認めなかった。