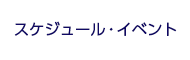「核もって絶滅危惧種仲間入り」は、毎日新聞万能川柳の2019年大賞受賞句である。作者の中林輝明さんは「子や孫たちの未来に核兵器はいらないと思うけれど、やみくもに反対をいうばかりでは句にならない」と言う。核兵器反対をしつこく言うけれど、こういう句を作れない私は「そうだね」と感心するばかりである。選者の仲畑貴志さんは「核兵器は人類を何度でも抹消できる。人類も絶滅危惧種に入っている。絶滅危惧種をつくり、それを守るという人類の傲慢。大きく深くデリケートな問題を提示している」と選評を述べている(※1)。そのとおりの句だと思う。
ところで、この句は7月にも秀逸とされていた。私はそれを受けて「オムニサイド(omnicide)を拒否するために」という文章を書いている。だから、「核持って絶滅危惧種仲間入り」その2、なのである。
オムニサイドの意味
オムニサイドは、(核兵器による)皆殺しという意味である。アメリカの哲学者ジョン・サマヴィル(1905年~96年)は、核兵器は自然界の万物ばかりか生と死との自然な関係を破壊する。通常の死は他の個体での生命の持続を可能にする細胞の再生産と再結合であるが、核による死は、細胞そのものを殺すことであり、通常の死よりも悪質である。新しい事態を表現するには新しい言葉が必要だ。それがオムニサイドである、としている(※2)。
私は、オムニサイドを拒否するためには、核による絶滅という客観的に存在する危機を主観的に認識することが必要だと考えている。だから、中林さんの受賞がうれしいし、仲畑さんの選評に共感するのである。
2017年、国連加盟国193ヵ国のうち賛成122ヵ国で採択された核兵器禁止条約は、核兵器使用による「壊滅的人道上の結末」を避けることは、人類にとって喫緊の課題だとしている。人類絶滅は、決して杞憂ではなく、現実に存在している危機だという認識は、国際社会の中で多数派なのである。
核兵器禁止条約が発効しても…
核兵器禁止条約は、批准国などが50ヵ国になり、その後90日が経過すれば効力が発生する。多分、今年中に発効するだろう。しかしながら、核兵器国はこの条約を無視するだろうから、当面、核兵器はなくならないし、人類は絶滅危惧種であり続けることになる。
ところで、核兵器国が核兵器に固執するのは、自国の安全保障のために核兵器が必要不可欠だと考えているからである。核兵器を持っていれば他国は自国を攻撃しないだろう。なぜなら、攻撃すれば核兵器によって反撃され手ひどい被害を受けることになるので、攻撃を思い止まるだろう、という論法である(核抑止論)。もし、この論法が普遍的ならば、北朝鮮やイランの核開発をとやかく言えないはずである。これらの国も自国と自国民の安全を確保する権利は認められているからである。けれども、アメリカなどは決して保有させようとしない。このような「俺は持つお前は持つな核兵器」という論法で世界が安全になることはありえない。なぜなら、それは不公平な論理だからである。そして、その論理が根底にある核不拡散条約(NPT)には、インドやパキスタンやイスラエルのように最初から乗らないか、北朝鮮のように考え直す国が出てくるのである。イランはどう出るのだろうか。
イランは「普通の国」になれ
アメリカのポンペオ国務長官は、イランに対し「普通の国」になれと言う。彼にとって、イランは「普通の国」ではなく、アメリカの要求を受け入れ、その行動を改めた時に「普通の国」になるようである(※3)。彼がイランに突き付けた「12項目の要求」の第2項は「イランはウラン濃縮を止めなくてはならない」とされている。しかしながら、国連安保理で決議されていた「包括的共同行動計画」(イラン核合意)は、限定的ではあるが、ウラン濃縮を認めているのである。トランプ政権は「イラン核合意」から一方的に離脱し、イランに不利益な要求を突き付け、制裁を強化しているのである。トランプたちは、どの国も、シンゾーのように、アメリカの要求は何でも受け入れると思い込んでいるようだが、イランは拒否している。アメリカの汚い手口に抵抗しているのである。
アメリカは核兵器使用をためらわない戦争を準備している
アメリカは、2018年に核態勢の見直し(NPR)を行い、核兵器によらない攻撃に対しても核兵器で反撃できるとし、使用可能な低爆発力核弾頭の製造を開始した。既に、新型の核弾頭を搭載した潜水艦発射型弾道ミサイルを実戦配備している(※4)。
2018年には、先に述べたように「イラン核合意」から一方的に離脱し、「イラン包囲網」をホルムズ海峡に張り巡らしている。
2019年には未臨界核実験が行われ、ロシアとの中距離核戦力(INF)全廃条約が失効し、早速、中距離ミサイル実験が再開されている。アメリカは紛争解決のために、核兵器を現実に使用する準備を整えているのである。
そして、忘れてならないことは、トランプは「核兵器を持っているのになぜ使用できないのか」と、1時間に3回、外交専門家に質問した人だということである(※5)。そんな男が核のボタンを持っているのである。
「原爆の父」の言葉
「原爆の父」といわれるロバート・オッペンハイマー(1904年~67年)は、1945年10月16日付のアインシュタインへの手紙で「もし原子爆弾が、この相いれない世界にあって、新兵器として加えられれば、…いつの日か人類は、ヒロシマを、そしてロスアラモスを罵る時がやってくるにちがいありません。世界の人々は結集しなければならない。いやそうしなければ完全に消滅することになるかもしれない」と書いている(※6)。相いれない世界というのは東西冷戦のことであり、ロスアラモスとはアメリカの核兵器開発の施設である。彼は、広島と長崎への原爆投下から3か月も経たないうちに、そのような予言をしていたのである。現在、アメリカとソ連の対立という形での冷戦はない。けれども、世界には敵意や憎悪や不信に根ざす対立が存在している。加えて、その対立の解消を望まず、むしろ扇動し、金儲けの手段としている勢力もはびこっている。彼らはそれぞれの思惑で核兵器に依存し、その禁止や廃絶に背を向けているのである。
他方、それに対抗し、絶滅危惧種から抜け出ようとする努力は、署名や集会、音楽、演劇、絵画、川柳を含む文学、教育実践などの形で積み重ねられている。核兵器廃絶への重要な一歩である核兵器禁止条約は発効しつつある。多様な形で、核兵器に反対し、これを禁止し、廃絶することは、人類生き残りのために不可欠な営みなのである。
(2020年3月7日記)
※1 毎日新聞 2020年3月7日付朝刊
※2 ジョン・サマヴィル著・芝田進午ほか訳『核時代の哲学と倫理』(青木書店・1980年)
※3 坂梨祥 「アメリカの正しさに『挑む』イラン」 学士会会報№941(2020年Ⅱ)
※4 『しんぶん赤旗』2020年2月6日付 国防総省は、新型核弾頭W76-2について「迅速で、より残存性の高い戦略兵器」、「拡大抑止の下支え」、「ロシアのような潜在的敵を念頭に置くもの」としている。
※5 『毎日新聞』2018年1月30日付夕刊。拙著『「核の時代」と憲法9条』(日本評論社・2019年)
※6 足立壽美『オッペンハイマーとテラー』(現代企画室・1987年)