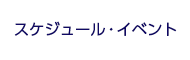―核不拡散条約(NPT)・条約法条約・核兵器勧告的意見の観点から―(*)
ベルント・ハーンフェルト
(訳:森川 泰宏)
ドイツ空軍第33戦闘爆撃航空団は、〔ドイツとルクセンブルクとの国境近くにある〕ビューヒェル航空基地に駐留している。同航空団は、北大西洋条約機構(North Atlantic Treaty Organization:NATO)の核協力の枠組み内で、〔戦術核兵器の搭載能力を有する〕トーネード戦闘機を用いて、同基地に配備されている〔米国から供給されたB61型〕核爆弾の輸送・投下訓練を行っており、戦時の際には、米国大統領による投下命令と米国の指揮系統を通じた作戦承認を経て、核爆弾を目標地点まで輸送することを任務とする。核爆弾の投下が米国の選定した目標に限定されるのにもかかわらず、〔このような核共有政策により〕戦時下のドイツ軍兵士は、NATOの支援の下で核兵器を「自由に処分する権限」を得ることになるのである。平時の核兵器使用に関する軍事演習において、演習用爆弾ではなく配備済みの核爆弾が用いられた例は見当たらない。
非核兵器国であるドイツは、核兵器不拡散条約(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons:NPT)(※1)の締約国として、NPT第2条に基づき、「核兵器その他の核爆発装置又はその管理をいかなる者からも直接又は間接に受領しない」義務を負っている。したがって、〔核兵器国である〕米国は、NPT第1条に基づき、「核兵器その他の核爆発装置又はその管理をいかなる者に対しても直接又は間接に移譲しない」義務を負うことになる。ドイツ政府は、1968年7月1日にNPTが署名開放される以前から核共有が存在していたことから、上記の義務が無制限に適用されるものではないと主張している(なお、西ドイツによるNPTの署名は1969年11月)。事実として、西ドイツは、1950年代には米国および英国により西ドイツに配備された核兵器運搬システムをすでに所有していた。重要なのは、核共有が国際条約に基づくものではないことに留意することである。核共有は北大西洋条約によるものではない。NATOの戦略の一部にすぎないのである。ドイツ連邦憲法裁判所は、NATOの戦略を修正するための条約は必要がないと判示している(※2)。NATOの戦略はドイツ政府の宣言によって放棄することができるのである。
NPTの文言は明確である。核共有に関連して配備された核兵器についての例外規定は存在しない。このことは、西ドイツがNPTに署名および批准するにあたり、戦時の際に核兵器を処分する権利について正式な留保を付したのかという問題を提起する。1969年11月にNPTに署名する際、西ドイツは、特に以下のように宣言している。
「ドイツ連邦共和国政府は… (4)ドイツ連邦共和国の安全保障がNATOにより引き続き保証されることを前提とし、NATOの集団安全保障の規則に全面的に関与することとする。」
署名当日にNPT締約国に送付した覚書において、西ドイツは、特に以下のように宣言している。
「連邦政府は… ドイツ連邦共和国およびその同盟国の安全保障がNATOまたはこれと同等の安全保障体制により引き続き保証されることを前提とする。」
1975年5月2日にNPTの批准書を寄託した際、西ドイツは、特に以下のように宣言している。
「ドイツ連邦共和国政府は… 2.ドイツ連邦共和国の安全保障が引き続きNATOにより保証されるものであり、ドイツ連邦共和国政府は、NATOの集団安全保障の規則により拘束されることを前提とする。」
いずれの宣言も、NATOの集団安全保障の規則の下でドイツの保護を保証するための兵器を明確に指定しているわけではない。西ドイツは、核共有の継続と〔当時、米国が推進していた多角的核戦力 (Multilateral Force:MLF)構想に含まれていたもので、欧州統合後にMLFを欧州の核戦力とする〕いわゆるヨーロピアン・オプションに特に関心を示していたものの(※3)、上記各宣言のなかで核兵器は明示的に言及されていないのである。上記各宣言の文言によれば、上記各宣言は、NATOが通常の兵器システムによりドイツを防衛することを排除してはいない。また、当時すでに実施されていた核共有がNPTの発効後も必然的に継続されるべきだということも、上記各宣言から読み取ることはできない。
それにもかかわらず、ドイツ政府は、NPTが核共有を禁止していないと主張している。その際に、署名および批准の際になされた上記各宣言にも言及しているのである。
上記各宣言が国際法上有効な留保であるのかについては、条約法に関するウィーン条約(条約法条約)(※4)により、国際法上の拘束力を有して規定されている。上記各宣言がNPTの内容を変更すること(たとえば制限すること)を意図していたとの解釈が示されるのであれば、条約法条約第2条1項(b)に基づく留保があるといえよう。この解釈において、留保が付されているかどうかの判断は、宣言の名称ではなく、専らその内容によることになる(※5)。
条約法条約第31条〔解釈に関する一般的な規則〕によれば、合意締結時に当事国が用いた文言が主観的に何を意味していたのかとは裏腹に、文言そのものが解釈上の決め手となる(※6)。鍵となる規定である条約法条約第31条1項は、慣習法であるとも考えられており、「条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする。」と規定されている。
条約法条約第19条(c)〔留保の表明〕によれば、条約の趣旨および目的と両立する留保のみが認められる。ドイツ政府により言及されているNATOの安全保障体制では、核共有の枠組み内で、戦時の際にドイツ政府の権限の下で行動するドイツ軍兵士に核兵器を移譲できるとされている。NPT第1条および第2条の趣旨は、核兵器国が非核兵器国に核兵器を移譲してはならず、また、非核兵器国が核兵器の管理をしないよう保証するものなのだから、この核兵器の引き渡しは、事実上、NPTを損なうものとなるであろう。核共有に関連する可能性がある他の条項は、NPT第1条および第2条には含まれていない。NPTの発効後も核共有(たとえば戦時の際に核兵器を自由に処分する権限の移譲)の有効性が継続するとしたら、NPTの文言および目的に逆行することになる。条約法条約第19条(c)により、上記各宣言は国際法上の留保の対象とみることはできず、または留保としては無効である。
上記各宣言は解釈宣言としてしか理解することはできない。解釈宣言は、条約規定を排除または変更することを目的とするものではなく、明確にすることのみを目的とする点で留保とは異なる(※7)。解釈宣言は、留保以上に条約全体の明白な文言および目的と矛盾してはならないものである。しかしながら、ドイツ政府の上記解釈では、戦時の際に核兵器を自由に処分する権限が移譲されることを意味してしまう。この解釈は、条約法条約第31条1項および第19条(c)に照らして不合理であって、法的効力を有しないというべきである。ドイツと米国との二国間による解釈が同一である可能性(ラスク書簡)(※8)については、戦時の際にNPTの中核的な規定を無意味にするものであって、NPT第1条および第2条の明確な規定に抵触するため、これをもって両国がNPTに違反する権利を得ることはできない。
核共有が実施されていることにより、核兵器使用に関する軍事演習に長年にわたる過去の実行があることでさえ、異なる評価を要するものではない。たしかに、条約法条約第31条3項(b)が「条約の適用につき後に生じた慣行」を考慮するよう要求していることは事実である。しかし、同条は、後に生じた慣行が「条約の解釈についての当事国の合意を確立する」場合にのみ適用される。NPT締約国のうち、多数の非核兵器国が核共有に反対していることは、同条が適用できないことを示している。
NPTの署名時にも批准書の寄託時にも、核共有の継続的な有効性に関して、西ドイツが国際法上有効な留保を表明しなかったことは、繰り返し強調されなければならない。また、NPTの条文解釈により、国際法上核共有を正当化することも不可能である。
すべてのNATO諸国がいまだにいわゆる「戦時留保(war reservation)」を用いていることは事実である。この「戦時留保」によれば、「戦争開始の決定がなされた」場合、(「その時点で条約はもはや権威を失うことになり」)、NPTは適用されないという(※9)。この一般には秘匿されている「戦時留保」に国際法上の効力があるとすれば、緊張や戦争が生じた際に、NPTまたはNPTに含まれる非核兵器国に対する核兵器不拡散の禁止が形骸化されてしまうことになる。
NPT第2条に国際法に基づく正式な留保が付された証拠は、いまだ一般に開示されてはいない。「戦時留保」の有効性については、国際法上の重大な疑義があり、一つは、手続面(条約法条約第23条〔留保に関連する手続〕に従ったNPT締約国に対して提供される〔書面または通報による〕確認済みの情報の欠如)であり、もう一つは、実体面(条約法条約第19条の意味でのNPTの趣旨および目的との整合性の欠如)である。
戦時に安全装置が解除された核兵器をドイツ軍兵士に移譲することは、NPTに違反する。同様に、ドイツ軍兵士による運用可能な核兵器の運搬は、NPT以外の国際法規範にも違反するものである。
これに関連して、国際司法裁判所(International Court of Justice:ICJ)の〔1996年の核兵器の威嚇または使用の合法性に関する〕勧告的意見(※10)によれば、〔国連憲章の第 2 条4 項(武力不行使原則)に違反し、かつ第 51 条(自衛権)のすべての要件を満たさない〕核兵器の威嚇または使用は、国際法違反であることに留意する必要がある。たしかに、ICJは、勧告的意見において、国際法の現状と利用可能な事実の要素とに鑑み、国家の生存そのものがかかった自衛の極端な状況における核兵器の威嚇または使用が合法であるか違法であるかについては、確定的に結論を出すことはできないとしている。この判断は、ICJでの審理において、核兵器使用の合法性を主張した国家のいずれもが、上記のような限定的な核兵器使用を正当化する妥当な要件を構成できなかったことによる。ICJは、将来、国際人道法の要求を満たす核兵器が登場する可能性を絶対的な確信を持って排除することができなかったのである(※11)。
重要なのは、国際人道法の原則および規則に違反しない武器が使用される場合にのみ自衛が認められるということを、ICJが勧告的意見の理由として繰り返し強調したことであって、ICJは、国連憲章第51条に基づき、「いかなる武力行使の手段であっても」、国際人道法により自衛権が制限されると判示している(※12)。つまり、核兵器を用いた自衛は、現在の兵器技術では核兵器は戦闘員と非戦闘員とを区別できず、特に放射線により不必要な苦痛を与えるものであり、また、国境を越えて中立国に影響を及ぼすことから、基本的に国際法上禁止されているということである。
国家の生存そのものがかかった自衛の極端な状況のための逸脱した自衛の規則を国際法から導き出すことはできない。核共有の枠組み内でドイツに配備されている核兵器は、国際人道法の要求を満たすことはできないのである。そのため、2006年版の〔交戦規則が簡潔に示された兵士が携帯するハンドブックである〕ポケットカードにおいて、ドイツ国防省は、ドイツ軍兵士による核兵器使用を明示的に禁止している(※13)。
ICJによれば、国際人道法の原則および規則は国際慣習法の一部である(※14)。これらの原則および規則は、ICJ規程第38条〔裁判の基準〕に基づいて効力を有する国際法であり、ドイツにおいては、〔ドイツ憲法に当たるドイツ連邦共和国〕基本法第25条〔国際法と連邦法〕に基づき、連邦法の主要な構成要素となっている。NPTについても、基本法第59条2項〔連邦の国際法上の代表〕に従って批准されて以来、ドイツ国内で適用される国際条約法とみなされている。
基本法第20条3項〔国家秩序の基礎、抵抗権〕によれば、ドイツ政府およびすべてのドイツ軍兵士は、例外なく当該法に拘束される。ドイツ政府およびすべてのドイツ軍兵士は、核兵器使用への関与を正当化することはできない。この場合、核兵器使用に責任のあるすべての者が国際法上の犯罪として刑事責任を問われることになるのである。
*本稿は、Bernd Hahnfeld, Widerspruch gegen die Behauptung der Bundesregierung, die von Deutschland im Rahmen der NATO praktizierte nukleare Teilhabe verstoße nicht gegen den Nichtverbreitungsvertrag(英語版題名:Opposition to the Federal Government's assertion that the nuclear sharing practiced by Germany within the framework of NATO does not violate the Non-Proliferation Treaty)を訳出したものである。原著はドイツ語であり、国際通信社プレセンザの翻訳チーム(Pressenza Translation Team)と西部諸州法律家財団のアンドリュー・リヒターマン(Andrew Lichterman)の協力により英語版が作成され、原著のドイツ語版と併せて2020年9月20日にIALANAドイツ支部のウェブサイトに掲載されるとともに、日本反核法律家協会を含む世界の関係NGOに頒布された。題名を直訳すると、「NATOの枠組み内でドイツにより実施されている核共有は核不拡散条約に違反しないとの連邦政府の主張に対する異議申立て」となる。訳出に際しては英語版を第一の典拠としているが、必要に応じてドイツ語版を参照した。出典は以下のとおりである。
・ドイツ語版
・英語版
ドイツ連邦共和国(Bundesrepublik Deutschland;Federal Republic of Germany)の国名表記については、東西ドイツ再統一の以前以後に対応して、基本的に西ドイツ、あるいは単にドイツと訳し分けた。また、一部の本文注については文末注に移動し、一部の注の表記を訳者が調整した。ウェブサイトのURLについては2021年4月30日の時点で接続を確認した。〔 〕は訳者が補ったもので訳注を兼ねている。なお、ドイツの核共有政策を含むNATOの核戦略全般については、小倉康久「NATOの核戦略:新戦略概念の検討」(浦田賢治編著『核抑止の理論:国際法からの挑戦』(日本評論社、2011年)所収、同書50‐62頁)に詳しいので、本稿と併せて参照されることをお勧めする。
【原註】
※1 NPT-BGBI, 1974 II, S.786.〔NPTの日本語公定訳は、外務省のウェブサイトで利用可能〕
※2 BVerfGE 104, S.151-214.
※3 Matthias Küntzel, Bonn und die Bombe, Deutsche Atomwaffenpolitik von Adenauer bis Brandt, Frankfurt/M, 1992, S.143.
※4 WVK-BGBl, 1985 II, S.927.〔条約法条約の日本語公定訳は、外務省のウェブサイトで利用可能〕
※5 Heintschel von Heinegg in Ipsen, Völkerrecht 6. Auflage, § 15 RdNr. 2.
※6 Wolfgang Graf Vitzthum in Wolfgang Graf Vietzthum, Völkerrecht 4. Auflage, 1.Abschnitt RdNr. 123; von Heinegg a.a.O., § 12 RdNr. 12.
※7 von Heinegg, a.a.O., §15 RdNr. 4.
※8 西ドイツのNPT加入前にドイツ連邦議会に提供された米国によるNPT解釈のこと。同解釈では、NPTは「戦争を行うことが決定されない限り、または決定されるまで」適用されるが、「戦時に条約の効力(controlling)は及ばない」とされる。See, IALANA Germany, An end to the atomic age, Annex 1〔pp.39-41〕and p.19, 2019. 同書は、IALANAのウェブサイトで利用可能。〔同書によれば、本稿でいう「ラスク書簡(Rusk Letter)」とは、当時のディーン・ラスク(Dean Rusk)米国務長官がリンドン・ジョンソン(Lyndon Johnson)米大統領に宛てた書簡に同封されていたもので、同盟諸国からのNPT草案に関する質問と米国による回答のことを指す。同書簡は、1968年7月9日に他の関連文書とともに米国上院に提出され、同日公開された。なお、上記の質問と回答部分の作成過程については、米国務省歴史課(Office of the Historian)のウェブサイトを見よ〕
※9 西ドイツ外務省に提出されたドイツ連邦議会の覚書とその附属書で再現されている〔ドイツ語訳されたラスク〕書簡(Bundestag/Drucksache 7/994)を見よ。これらの覚書等については、IALANAドイツ支部のウェブサイトで利用可能。
※10 Advisory Opinion of the International Court of Justice of 8. July 1996, printed in IALANA, Atomwaffen vor demInternationalen Gerichtshof, Münster, 1997.〔同勧告的意見の英語正文は、ICJのウェブサイトで利用可能〕
※11 勧告的意見94項。
※12 勧告的意見の40項、41項、42項、78項を見よ。42項では「均衡性原則は、それ自体としては、あらゆる状況における自衛による核兵器使用を排除するものではない。しかし、同時に、自衛の法の下で均衡のある武力行使は、合法であるためには、特に人道法の原則および規則を含む武力紛争で適用される法の要求を満たさなければならない。」としている。
※13 Druckschrift Einsatz Nr.03, Humanitäres Völkerrecht in bewaffneten Konflikten –Grundsätze–, August 2006, DSK SF009320187.〔BITS(Berlin Information-center for Transatlantic Security)のウェブサイトで利用可能〕
※14 勧告的意見79項。
初出・機関誌『反核法律家』107(2021年夏号)
バックナンバー申込フォーム