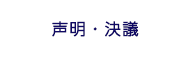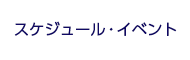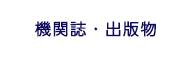許されない核兵器による威嚇
―核の威嚇・恫喝・脅しの国際法上の評価―(*)
核政策法律家委員会(LCNP)上席研究員
ジョン・バロース
(訳:森川 泰宏)
冷戦終結後に広まった核時代のリスクが減少しているという楽観的な見解〔いわゆる「核の忘却」〕に反して、核兵器が実際に使用される脅威は増大している。
2017年の夏と秋には、米国と北朝鮮とが相互に扇動的な核破壊の警告を交わした(※1)。2019年9月には、カシミール地方をめぐるインドとの国境紛争に関連して、パキスタンが核戦争の可能性に言及した(※2)。直近では、北朝鮮の最高指導者である金正恩総書記は、折に触れて、自国の基本的な利益を守るために核兵器に訴える用意があると表明している(※3)。最も憂慮すべきなのはロシアのケースであり、〔ロシアによるウクライナ侵攻が開始された〕2022年2月24日に行われたプーチン(Vladimir Putin)大統領の演説(※4)から現在に至るまで、米国とその北大西洋条約機構(NATO)同盟国とがロシアによる全面侵攻からウクライナを守るために介入した場合に、核兵器に訴える可能性を繰り返し示唆している。
このような威嚇(threat)は、核兵器の使用による人道・環境上の破局のリスクを著しく高めるものであって、断じて受け入れることはできない。この点、世界の大国を含む政府間フォーラムであるG20〔先進7か国(G7)と欧州連合(EU)に新興国を加えた主要20か国からなる金融・世界経済に関する首脳会合〕が、2022年11月のバリ・サミットで採択した首脳宣言において示した見解は注目に値する。同宣言では、「平和と安定を守る国際法と多国間システムを堅持することが不可欠である。これには、国連憲章に謳われている全ての目的及び原則を擁護し、武力紛争における市民及びインフラの保護を含む国際人道法を遵守することが含まれる。核兵器の使用又は使用の威嚇は許されない(The use or threat of use of nuclear weapons is inadmissible)」と述べられている(※5)。
このG20の見解は、明らかにロシアによる核威嚇を意識したものであるが、その文言上、ロシアの状況に限られるものではない(※6)。同様の見解は、2023年9月のニューデリー・サミットで採択された首脳宣言でも繰り返し述べられている。
法的側面
核兵器の使用又は使用の威嚇は「許されない(inadmissible)」とするG20の首脳宣言は、政治的・道徳的規範の表明にすぎないのであろうか、それとも、何らかの法的側面を有しているのであろうか。結論からいえば、inadmissibleという文言には、法的な含意があるといえる。裁判においては、証拠が受理できる(admissible)のか、それとも受理できない(inadmissible)のかが判断されるものである。さらに、核兵器を使用するとの威嚇は、受け入れ難い不当なものであるのみならず、国際法に違反すると評価し得る確かな法的論拠がある。当該論拠は、武力行使の合法性を規律する法(jus ad bellum(ユス・アド・ベルム))と、戦闘行為を規律する法(jus in bello(ユス・イン・ベロ))、すなわち、武力紛争法(LOAC)又は国際人道法とで構成されている。
国連憲章第2条4項は、「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない」と規定している。ある武力の行使が国連憲章第2条4項に違反するのならば、そのような武力に関わる威嚇もまた同条に違反することになる。国際司法裁判所(ICJ)が1996年の「核兵器の威嚇又は使用の合法性に関する勧告的意見」(核兵器勧告的意見)において広範に述べたように、「国連憲章第2条4項における武力の『行使』と『威嚇』の概念は、ある事例において武力の行使自体が違法ならば、その理由が何であれ、そのような武力の行使をするとの威嚇も同様に違法であるという意味において、一体となっている」のである(※7)。
したがって、侵略的な攻撃の一部として核兵器を使用するとの威嚇は違法と評価される。このことが、ウクライナ侵攻を支援するために行われたロシアによる核威嚇にも当てはまることに疑いの余地はない。
翻って、ロシアのケースのように侵略的な攻撃の一部として行われた場合以外において、国家が核兵器を使用するとの威嚇を行った場合の法的評価はどうであろうか。ICJの判示によれば、自衛における武力の行使又は武力による威嚇は、必要性を満たし、かつ均衡性のとれたものでなければならない(※8)。自衛のために核兵器を使用するとの威嚇は、このような必要性と均衡性の要件を満たさない限り、jus ad bellumの下で違法と評価される。この文脈では(※9)、自衛のための武力の行使は、対応する侵略的行為と妥当な関係性を有し、また、攻撃を受けた国から敵軍隊を撤退させることなど、自衛のための武力の行使の合法的な目的とも妥当な関係性を有していることが必要となる。多くの場合又は全ての状況において、自衛のための核兵器の先制使用は、jus ad bellumの問題として、必要性と均衡性の要件を満たすことができないと思われる。特に、ICJは、均衡性を評価する際に、エスカレーションのリスクも考慮に入れなければならない点を指摘している(※10)。よって、近年の北朝鮮による核威嚇が均衡性の要件を満たしているとはいえない。
また、ICJは、攻撃のためであれ、自衛のためであれ、核兵器を使用するとのいかなる威嚇であっても、国際人道法、すなわち、jus in belloを遵守するものでなければならないと判示している。一般的な見解として、ICJは、「ある想定される兵器の使用が人道法の要件を満たさないのであれば、そのような兵器の使用に関わる威嚇もまた、この法に反することとなる」と述べている(※11)。この原則に従えば、核兵器の使用が違法であるのなら、核兵器の使用の威嚇もまた違法と評価されることになる。
例外的なケースを除けば、典型的なケースでの核兵器の使用は、たとえ自衛のためであっても、国際人道法の下で違法と評価される(※12)。ICJは、この結論を受け入れる方向に大きく舵を切り、「核兵器の威嚇又は使用は、武力紛争に適用される国際法の規則、特に人道法の原則と規則に一般的には違反するであろう」と判示したのである(※13)。しかしながら、ICJは、国家の生存そのものがかかった自衛の極限状況に関しては、いずれにせよ、結論することはできないとしている(※14)。核兵器勧告的意見から約30年が経過した現在、国際社会は、ICJが回避したこのような不確実性を乗り越える必要がある。
威嚇についてのICJの判断
侵略的又は不均衡な武力による威嚇を禁止する国連憲章の要件に関するICJの判断については、国連憲章と、自衛のための武力の行使が必要性を満たし、かつ均衡性のとれたものでなければならないという確立された規則とに立脚したものであることから、異論を差し挟む余地はない。これとは異なり、国際人道法〔すなわち、jus in bello〕に違反する兵器を使用するとの威嚇をも違法とするICJの判断の論拠は、核兵器勧告的意見それ自体からは明らかでなく、条約法やICJの判例法から、これを導き出す原則を容易に確認することも困難である。
しかし、違法な武力による威嚇それ自体を違法とする判断は、現代の最も重要な条約である国連憲章に根ざしたものである。国連憲章は、違法な武力による威嚇の違法性が国際人道法の違反にまで及ぶか否かという点を直接規定してはいないものの、武力による威嚇の合法性については、武力の行使の違法性と一体のものとして判断すべきことを示唆している。ICJが、国連憲章第2条4項に基づき、武力を行使するとの威嚇が「その理由が何であれ」違法である場合に、武力の行使の違法性について言及していることは、この示唆と合致する(※15)。さらに、国連の目的に反する武力による威嚇が国連憲章第2条4項で禁止されていることは、侵略的又は不均衡な威嚇の禁止から踏み出したICJの判断に一定の論拠を与えるものである。国連憲章第1条に規定される国連の目的には、平和と安全の維持、人道的性格の問題の解決や人権尊重の促進における協力などが含まれる。
上記のような国連憲章上の考慮事項を超えて、ICJは、自らの裁量で国際人道法に違反する兵器を使用するとの威嚇が違法であるという原則を宣言したようにみえなくもない。ICJは、国際法の一般的な問題を取り扱う世界で最高の裁判所なのであり、その判事には、著名な国際法律家が含まれている。ある司法制度における最高の裁判所が法を発展させたり、換言すれば、既存の原則を可視化したりすることは特に珍しいことではない。
国際法においては、違法行為の準備行為と違法又は犯罪となる違法行為それ自体とを区別することがある。このような傾向は、国際刑事裁判所(ICC)ローマ規程に規定される侵略犯罪でも見受けられるものであり、ローマ規程では、侵略の「計画」又は「準備」により個人が有罪とされる可能性があるが、それは、国家による〔国連憲章の明白な違反を構成する〕「侵略行為」が実際に行われた場合に限られる旨が規定されている〔第8条bis 1項〕。このアプローチが国家責任の領域で採用された場合、条約に違反する場合に限り、威嚇は違法と評価されるのであり、国連憲章上の侵略の威嚇のケースでも同様に取り扱われることとなろう(※16)。
国際人道法に違反する核兵器を使用するとの威嚇は、確かに具体的かつ信憑性のある威嚇を構成するといえるが、単に侵略的な攻撃を可能とする軍事力を取得することなどの準備行為とは異なるものである。生物兵器と化学兵器の場合を念頭に置けば、ICJの判断の妥当性を理解することができよう。生物兵器と化学兵器の使用は、無差別かつ制御不可能な影響を伴う攻撃を禁止する国際人道法に違反し得るものである(※17)。さらに、普遍性をほとんど達成した〔軍縮〕条約である化学兵器禁止条約(CWC)では、化学兵器の保有及び使用を禁止しており、同様に、生物兵器禁止条約(BWC)では、生物兵器の保有を禁止し、既存の生物兵器の使用の禁止を強化している。はたして、このような生物・化学(BC)兵器を使用するとの具体的かつ信憑性のある威嚇を合法と評価してよいのであろうか。軍備分野以外をみると、集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約(ジェノサイド条約)では、ジェノサイドの教唆、共同謀議又は未遂が禁止の対象とされているが、威嚇は禁止されていない。しかし、ジェノサイドを行うとの具体的かつ信憑性のある威嚇を合法と評価できるかは非常に疑わしいのではなかろうか。
国際人道法上、威嚇は、部分的に国際的禁止の対象となっている(※18)。国際人道法の重要な法文書である1977年のジュネーブ諸条約第一追加議定書では、〔国際的な武力紛争において〕「文民たる住民の間に恐怖を広めることを主たる目的とする暴力行為又は暴力による威嚇」を禁止する条項がある(※19)。また、生存者を残さないとの威嚇を禁止する条項もある(※20)。
このような禁止条項については、二つの異なった観点から考えることができる。一つには、このような部分的な禁止という性質は、国際人道法に違反する兵器を使用するとの威嚇が包括的に禁止されていないことを示しているということである。もう一つは、禁止された行為を実行するとの威嚇もまた禁止されるという基本原則を示しているということである(※21)。
国際法の進展
後者の観点については、2017年に行われた核兵器禁止条約(TPNW)の条約交渉や2018年に採択された国連の自由権規約委員会による〔国際人権法上の〕生命に対する権利に関する一般的意見36において、近年示された国際法の進展と調和するものである。自由権規約委員会は、一般的意見36において、「大量破壊兵器、特に核兵器の威嚇又は使用は、・・・生命に対する権利の尊重と両立しないものであり、国際法上の犯罪に該当し得る」との見解を示している(※22)。
TPNWは、核兵器の威嚇又は使用が違法であるという世界の大多数の国の見解を表明したものとしては、最も新しいものである。以前にも、このような見解は、ICJでの陳述の際に表明されており、また、核兵器の使用の違法性に関しては、1961年にまでさかのぼる多くの国連総会決議において表明されてきた(※23)。さらに、1967年のトラテロルコ条約を嚆矢として、非核兵器国は、非核兵器地帯(NWFZ)の条約交渉に取り組んでおり、成立した各非核兵器地帯条約には、同条約を批准した核兵器不拡散条約(NPT)上の5核兵器国〔N5:米国、英国、フランス、ロシア、中国〕に対し、地帯構成国への核兵器の使用又は使用するとの威嚇を行わないことを義務付ける議定書が附属している(※24)。
バリ・サミットでのG20首脳宣言の採択からさかのぼること5か月前の2022年6月に開催されたTPNWの第1回締約国会議(1MSP)において、ウィーン宣言〔1MSPの「宣言」〕が採択された。同宣言では、締約国は、「核兵器のいかなる使用も、使用の威嚇も、国際法への違反であることを強調し」、「あらゆる核の威嚇について、それが明示的になされようと、黙示的になされようと、また、その状況にかかわりなく、これを明確に非難する」と述べられている。2023年末にニューヨークで開催された第2回締約国会議(2MSP)においても、これらの点が改めて強調されている。TPNW自体は、締約国に対し、「いかなる場合にも」、「核兵器を使用すること又は使用するとの威嚇を行うこと」を「行わないこと」を義務付けている。ただし、TPNWの締約国に核保有国は含まれていない。
このような国際法の進展は、国際人道法に違反する兵器を使用するとの威嚇、つまり、少なくとも一般論として、核兵器を使用するとの威嚇を違法としたICJの判断の妥当性をさらに裏付けるものでもある。そして、核兵器の場合に重要な懸案事項となることが明らかなエスカレーションのリスクについては、均衡性を評価する際にこれを考慮に入れなければならない点も、繰り返し特に強調しておく必要がある。
国際法上の「威嚇」の定義を試みるまでもなく、政府声明による具体的かつ信憑性のある要求が違法な威嚇に該当すると断言できる場合がある。核保有国が関与する武力紛争など利害関係の大きい具体的な状況を想定してみよう。その際に伝えられるメッセージは、Xを控えなければ又はYを行えば、核兵器に訴えるというものである。このような政府声明は、疑いなく法的に認識可能な威嚇といえる。このような想定は、ウクライナ侵攻当初になされたプーチンの威嚇を正しく描写するもので、プーチン大統領は、ウクライナでの軍事作戦にNATO諸国が「介入」した場合、核兵器に訴える用意があると表明したのである。
核攻撃を受けた場合や、より一般的には、重大な利益がかかっている場合に限り、核兵器に訴える用意があることをあらかじめ宣言する国家政策の法的評価はどうであろうか。このような政策には特定の威嚇が含まれていないことから、違法ではないと主張することもできよう。重大な利益への言及やこれと同様の表現が曖昧であることは確かである。それでも、核攻撃に対して応戦的又は先制的な核攻撃が行われ得る又は行われるという国家政策上の基本原則(ドクトリン)で示されるシグナルは、実際に核兵器が使用される状況で発せられなくとも、焦点を絞った信憑性のあるものといえる。
より広範にいえば、特定の威嚇が違法と評価されるのなら、そのことは、核抑止政策の基本原則と仕組みの違法性をも示すものであって、少なくとも正統性が欠如していることを示している。核兵器勧告的意見において、ICJは、「いわゆる『抑止政策』として知られる慣行にここでは言及するつもりはない」と述べている(※25)。しかし、ICJでの口頭陳述において米国が自ら述べたように、「抑止政策と抑止手段の使用の合法性とを切り離すことは不可能」なのである(※26)。
ロシア・ウクライナ間の紛争やその他の地域でも、核の脅威が高まっていることは、まことに憂慮すべきことである。それでもなお、その重要性を過大評価すべきではないものの、前向きな傾向も見受けられる。G20サミットやTPNWの会合において、核威嚇に対する規範的な反論がなされたことは心強い。また、ロシアによる核威嚇に対して、ほとんどの局面で、これに対応する核威嚇を米国やNATO諸国が自重していることにも励まされる。
核兵器を使用するとの威嚇を禁ずる規範には、〔政治的・道徳的規範にとどまらない〕確固とした法的根拠がある。当該法規範を国内的・国際的な理解と実践の中により深く根付かせるよう力を尽くすことが、各国政府と市民社会に求められるものとなろう。
* 本稿の出典は以下のとおりである。
John Burroughs, “The Inadmissibility of Nuclear Threats,” Arms Control Today, Vol. 54 (April 2024), available at <https://www.armscontrol.org/act/2024-04/features/inadmissibility-nuclear-threats>.
著者のジョン・バロースは、法学者と弁護士を中心として構成される米国の代表的な反核NGOである核政策法律家委員会(LCNP)の上席研究員(Senior Analyst)。ハーバード大学を卒業後、カリフォルニア大学バークレー校で博士号(JD、Ph.D)を取得。ラトガース大学法科大学院の特任教授として国際法の教授歴もある。アクティビストとしては、1996年のICJ核兵器勧告的意見の際に、NGOを初めとした市民社会を含む公聴会に参加した国際反核法律家協会(IALANA)とLCNPの法律コーディネーターを務めたことを皮切りに、1999年から2020年までのおよそ20年間にわたり、NPT再検討サイクルやTPNWの条約交渉などにおいて、LCNPの事務局長として精力的な活動に従事してきたほか、特筆すべき個人の活動として、2016年のICJ「核軍備競争の停止と核軍備の縮小に関する交渉義務事件」(いわゆる「核ゼロ裁判」)では、マーシャル諸島共和国の弁護団の一員としても活躍した。また、本稿が掲載された米国のシンクタンク・軍備管理協会(ACA)発行の『アームズ・コントロール・トゥデイ』誌を初め、軍縮・軍備管理分野の専門誌に多数の論稿を寄稿している。現在でも参照される主要著書として、The Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons: A Guide to the Historic Opinion of the International Court of Justice (Lit Verlag, 1997)(同書の日本語訳として、山田寿則・伊藤勧共訳(浦田賢治監訳)『核兵器使用の違法性:国際司法裁判所の勧告的意見』(早稲田大学比較法研究所、2001年))がある。
本稿は、2023年11月8日に米国のニューヨーク州弁護士会(NYSBA)国際部が主催したシンポジウム「核兵器と国際法:ロシアのウクライナ侵略に照らして生じる喫緊の課題」(Nuclear Weapons and International Law: The Renewed Imperative in Light of the Russian Invasion of Ukraine. NYSBAのウェブサイト<https://nysba.org/events/nuclear-weapons-and-international-law-the-renewed-imperative-in-light-of-the-russian-invasion-of-ukraine/>で詳細が確認できる)での著者の報告に基づいている。ロシアによるウクライナ侵攻を契機として、近年特に耳目を集める核兵器による威嚇(恫喝、脅しとも表現される)について、国際法の側面からの法的評価を試みるものであり、核兵器による威嚇をめぐる国連憲章や国際人道法の観点からの基本的な論点に加え、従来の法的アプローチを補完・強化する近年の傾向として特に注目される国際人権法の観点からの核兵器の威嚇又は使用の違法性の展開に至るまで、簡にして要を得た論評からは多くの示唆を得ることができるだろう。とりわけ、具体的な核兵器による威嚇と一般的な核抑止政策の慣行とを結びつけて評価できるのか、あるいはできないのかは、これを是とする核兵器廃絶を目指す市民社会にとって、あらゆる手段を駆使してその克服が試みられなければならない最重要課題である一方で、より精緻な学術的な議論に当たっても、いわゆる核抑止派・核軍縮派の如何にかかわりなく、繰り返し問われ続けなくてはならない主要論点であるべきなのであって、実務と調査・研究の両者に携わる著者の視座は、この点に自覚的であるように思われる。これら本稿の内容を踏まえ、本稿の副題である「核の威嚇・恫喝・脅しの国際法上の評価」は訳者が付け加えたものである。
核兵器による威嚇をめぐる諸問題については、核の復権とも評される核兵器を取り巻く状況が一段と厳しさを増すなか、2026年のNPT再検討会議に至る一連の再検討サイクルにおいても、引き続き激しい議論の対象となることが予想される。この点について、LCNPが2022年のNPT再検討会議の際に公表した提言書として、「核不拡散レジームに対峙する核威嚇と核共有」(日本反核法律家協会(JALANA)のウェブサイト<https://www.hankaku-j.org/data/07/240109.html>で利用可能)もある。本稿と併せて参照されるならば、2026年のNPT再検討会議で交わされる法的な議論・論点をあらかじめ理解し、これに備える足掛かりとしても参考となる点があろう。
ウェブサイトのURLについては、2024年7月8日の時点で接続を確認した。また、訳出に当たって、一部の注の表記を訳者が調整した。〔 〕は訳者が補ったものであり、訳注を兼ねている。
【註】
- John Burroughs and Andrew Lichterman, “Trump’s Threat of Total Destruction Is Unlawful and Extremely Dangerous,” InterPress Service, September 25, 2017〔available at <https://www.globalissues.org/news/2017/09/25/23539>〕.
- “Pakistan’s Khan Warns of All-Out Conflict Amid Rising Tensions Over Kashmir; Demands India Lift ‘Inhuman’ Curfew,” UN News, September 27, 2019,〔available at〕<https://news.un.org/en/story/2019/09/1047952>. 2024年初頭に、インドのモディ(Narendra Modi)首相は、パキスタンとの間の緊張に関連して、インドの核兵器能力について言及した。Pallak Nandi and Vimal Bhatia, “Our nukes not for Diwali: PM Narendra Modi on Pakistan's N-threat,” The Times of India, April 22, 2019,〔available at〕<https://timesofindia.indiatimes.com/elections/news/our-nukes-not-for-diwali-pm-on-pakistans-n-threat/articleshow/68982495.cms>.
- Josh Smith, “Explainer: How Could North Korea Use Its Nuclear Weapons?” Reuters, December 20, 2023〔available at <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/how-could-north-korea-use-its-nuclear-weapons-2023-12-21/>〕.
- クレムリンが公開している演説の文字起こし(スクリプト)によれば、当該部分の内容は以下のとおりである。「私は今、外部からこれらの展開に介入しようとする皆さんにとても大事なことを申し上げたい。誰が我が国の邪魔をしようとも、あるいは我が国と国民に脅威を与えようとも、ロシアは即座に対応し、その結果はこれまでに見たこともないようなものになるであろうことを、あなた方は知っておかなければならない、と」。〔available at〕<http://www.en.kremlin.ru/events/president/transcripts/67843>.
- “G20 Bali Leaders’ Declaration,” November 15-16, 2022, para. 4,〔available at〕<https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100421967.pdf>〔原文のリンクはリンク切れのため、外務省のウェブサイトで提供されている英文のリンクに変更した。日本語訳(仮訳)については、外務省のウェブサイト<https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100422034.pdf>で利用可能。本文中の日本語訳は訳者が一部変更を加えている〕.
- もっとも、2024年2月24日のG7(カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国、米国)による首脳声明では、その範囲が限定されており、「ロシアのウクライナに対する侵略戦争の文脈における、ロシアによる核兵器の使用の威嚇、ましてやロシアによる核兵器のいかなる使用も許されない」と述べられている。The White House, “G7 Leaders’ Statement,” February 24, 2024, para. 2,〔available at〕<https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2024/02/24/g7-leaders-statement-7/>〔日本語訳については外務省のウェブサイト<https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100646139.pdf>で利用可能〕.
- Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J Reports 1996, para. 47,〔available at〕<https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf>.
- Ibid., para. 41
- jus ad bellumにおける均衡性の要件は、攻撃によって生じる付随的損害や傷害が、想定される軍事的利益と比べて過度ではないことを要件とする国際人道法上の比例(均衡)性原則とは異なるものである。
- Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, supra note 7, para. 43.
- Ibid., para. 78.
- See, “End the War, Stop the War Crimes,” Lawyers Committee on Nuclear Policy, April 21, 2022, pp. 5-6,〔available at〕<https://www.lcnp.org/s/4-21-22-russia-ukraine_lcnpstatement2.pdf>; Charles J. Moxley Jr., John Burroughs, and Jonathan Granoff, “Nuclear Weapons and Compliance With International Humanitarian Law and the Nuclear Non-Proliferation Treaty,” Fordham International Law Journal, Vol. 34, No. 4 (2011), pp. 595ff〔available at <https://ir.lawnet.fordham.edu/ilj/vol34/iss4/1>〕.
- Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, supra note 7, para. 105(2)E.
- Ibid.
- Ibid., para. 47.
- 国連国際法委員会(ILC)は、「威嚇の行為、教唆又は未遂を明確に禁じる規則もあり、その場合、威嚇、教唆又は未遂それ自体が違法な行為となる」と述べて、この立場をとっている。 Yearbook of the International Law Commission, 2001, Vol. 2, Part 2, A/CN.4/SER.A/2001/Add.1 (Part 2), 2007, p. 61〔available at <https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_2001_v2_p2.pdf>〕.
- 国際人道法の一般的な諸規則に加えて、いまだ少数の国の批准にとどまっているものの、〔2010年の〕改正ローマ規程では、生物兵器の使用を明確に戦争犯罪と規定している(第8条(2)(b)(xxvii))。化学兵器の使用については、〔1925年の〕ジュネーブ毒ガス議定書の文言をそのまま用いて、「窒息性ガス、毒性ガス又はこれらに類するガス及びこれらと類似のすべての液体物質又は考案」の〔内戦を含む〕使用を禁止する条項(第8条(2)(b)(xxviii))により、特に犯罪性を有するものと考えられる。
- 国際法における法の一般原則の認定には、国内の法制度に組み込まれた諸原則も関係する。例えば、米国の国内法では、特定の状況下での威嚇又は脅迫を禁止している。コロラド州法では、「脅迫又は物理的行為により、故意に他者を差し迫った深刻な身体的傷害の恐怖に陥らせ又は陥らせようとする者は、脅迫の罪を犯したものとする」と規定されている(コロラド州法第18編第3章第206条)。また、連邦法では、「州際通商又は外国取引において、他者を誘拐し又は他者を侵害する脅迫を含む情報」を伝達することは犯罪となる(合衆国法典第18編第875条(c))。
- ジュネーブ諸条約第一追加議定書第51条(2)〔日本語公定訳については、外務省のウェブサイト<https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_11a.pdf>で利用可能〕。米国の「2022年版核態勢見直し(NPR)」では、「長年にわたる米国の政策は、文民及び民用物を故意に威嚇するものではない」と述べられている。 “2022 Nuclear Posture Review,” October 27, 2022, p. 8,〔available at〕<https://media.defense.gov/2022/Oct/27/2003103845/-1/-1/1/2022-NATIONAL-DEFENSE-STRATEGY-NPR-MDR.PDF>. このような表明は、軍事目標を標的とする現実から切り離して表面上だけをみれば、同条の禁止事項と整合性がある。
- ジュネーブ諸条約第一追加議定書第40条。
- Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, Vol. I (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), p. 162.
- UN Human Rights Committee, “General Comment No. 36 (2018) on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the Right to Life,” CCPR/C/GC/36, October 30, 2018, para. 66〔available at <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/CCPR/CCPR_C_GC_36.pdf>. 日本語訳(仮訳)については、日弁連のウェブサイト<https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2021/HRC_GC_36j.pdf>で利用可能。なお、TPNWは、その規定ぶり、特に、前文、第6条(被害者に対する援助及び環境の修復)及び第7条(国際協力及び援助)の規定から、単なる軍縮条約の範疇にとどまらず、国際人権条約の性質を持つものと捉えることもできるところ、一般的意見36ないし生命に対する権利との関係も踏まえ、国際人権法の観点からTPNWの意義を概説した論稿として、ボニー・ドチェルティ(森川泰宏訳)「核兵器禁止条約(TPNW)と国際人権法」反核法律家108号(2021年)50-56頁(JALANAのウェブサイト<https://www.hankaku-j.org/data/01/220202_202101.html>で利用可能)を参照せよ。端的にいえば、TPNWは、核軍縮に人道的(人類的)アプローチ(humanitarian approach)をもたらしたものと理解されている(同論稿50頁)〕.
- See, UN General Assembly, “Declaration on the Prohibition of the Use of Nuclear and Thermo-Nuclear Weapons,” Res. 1653 (XVI), November 24, 1961〔available at <https://digitallibrary.un.org/record/662077?ln=en>〕.
- 核兵器国による同議定書の批准は、完全にはほど遠く、かなり限定的なものにとどまる場合もある。他方、NPTの内と外において、核兵器国は、条件付きながら、ほとんどの場合に非核兵器国に対して核兵器を使用せず、核兵器を使用するとの威嚇も行わないとする消極的安全保証(NSAs)を提供している。また、当然のことではあるが、ICJは、非核兵器地帯条約とその附属議定書及びNSAsは、核兵器の威嚇又は使用の包括的な禁止を確立するものではないと判示している。 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, supra note 7, para. 63. これらの問題を概説した論稿として、Anna Hood and Monique Cormier, “Nuclear Threats Under International Law Part I: The Legal Framework,” NAPSNet Special Reports, March 1, 2024〔available at <https://nautilus.org/napsnet/napsnet-special-reports/nuclear-threats-under-international-law-part-i-the-legal-framework/>. なお、同論稿(アンナ・フード/モニカ・コルミエ「国際法下における核の威嚇(パートⅠ):法的枠組みについて」)は、長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)のウェブサイト<https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/topics/45901>にも日本語要旨付きで掲載されている〕.
- Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, supra note 7, para. 67〔なお、核兵器勧告的意見における核抑止政策への他の言及箇所の概要とその法的評価については、例えば、藤田久一「核兵器をめぐる法と戦略の交錯」世界法年報18号(1999年)66-87頁(J-STAGE<https://doi.org/10.11388/yearbookofworldlaw1986.1999.66>で利用可能、藤田久一『核に立ち向かう国際法:原点からの検証』(法律文化社、2011年)に再録)、特に70頁以下を参照せよ。藤田は、核兵器勧告的意見は、「抑止政策の法的位置付けを直接には避けつつ、自衛の脈絡に持ち込んだ。つまり、抑止政策を自衛権という法概念を通じて『法化』(法的フォーミュラ化)しようとした」と指摘する(同論稿72-73頁)〕.
- Verbatim record, CR 95/34, November 15, 1995, p. 63,〔available at〕<https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/95/095-19951115-ORA-01-00-BI.pdf>.