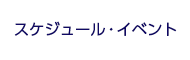被爆者の心の被害とは何であるかをクリアーカットに述べたいと思う。だが、なかなか難しい。
あれとこれとこれ、と並列的に項目で並べられればいいのだが、いくつかの要素が互いに立体的に入り組みからみ合っているうえに、時間とともに変化してくるからである。そして「体の被害」「暮らしの被害」にともなう裏側の病状にもなっているからである。ここでは、だれでも了解できる「訴え」から入り「訴えられないもの」「外傷記憶・記憶の抑圧と再現のメカニズム」に進み「被爆後受けたスチグマや生活苦により強化される」ようす、「老いを迎えたいまの心の被害」へと進む。このことはいろいろな「心の被害」があることを意味しない。いろいろな面から、表層から深層へ、過去から現在へ(ときには、現在から過去へ)と視点を移してみることにより被爆者ならだれでも受け、いまも続いている「心の傷」の立体的な構造を明らかにしようとしているのである。だがその傷の深さ、濃淡、受け止め方は画一的ではなく、各人各様なのである。だから、クリアーカットにいってしまうと逆に真実から遠くなる。
ここではその恐れを承知で、できるかぎりわかりやすく構造の大略を述べる。
「聞けば、知ればだれでもわかる」心の被害から「自身も自覚しない」心の傷へ
本書でも被爆当時の悲惨な体験や見聞が語られた。あまりの重さに途中で投げ出したくなった人もあるだろう。一瞬にして消えたまち、目の前で肉親・知人が死んでいくさま、大量の異形の死体、幽鬼のごとき被災者の列、手助けできない自分、末期の水さえ与えられなかった自分・・・・・。これらの体験をすればだれでも「心に深い傷」を受ける。それを聞き、知った人はだれでもそのことを理解する。それは、その深さゆえに何年経っても忘れるものではない。ふつうの感覚をもった人なら、自分の経験から類推してだれでもそのことを了解するのである。事実、直接被爆者から聞いたり、書いたものを読んだり、記録フィルムなどを見た人はそれを「心の被害」として理解し共有できる。このことは「心の被害」の原点・土台であり、被爆者の多くが語り・書き綴っているところである。だが、その真相を伝えようとするとき、だれでもが一様に「筆舌に尽くしがたい」としている。どうにも伝えきれないものがあるということ――伝達手段の限界というか、体験共有の限界を感じているのがわかる。事実、受けた「心の傷」の深さはわれわれの想像を超えるものである。それを教えてくれるのが記憶の欠損であり感情麻痺である。
不意打ちに、前代未聞の危機的・極限的状況におちいったとき、人は記憶や認知や感情などの機能をフリーズさせるか、バリアを張って入力を制限する自己防衛本能が作動する。被爆下でも同じことがおこっている。よく聞いてみると、程度・期間のちがいはあるが、記憶欠損がおこっている。
長期の記憶欠損のなかで、いくつかの鮮明な記憶断片がある人、ところどころ記憶の欠けている人、なんとなくうすぼんやりとしかおぼえていない時間をもつ人、肉親を探すことに意識が占領され、結果的にそれ以外のことがかすんでいる人など、さまざまである。定説では、しっかりした記憶の保持は七~八歳以上でないと難しいとされている。被爆者の場合、七~八歳以上の人にこの記憶欠損がおこっている。したがって、被爆者の手記は「記憶として残っている部分からできている」と考えるべきである。記憶欠損・ぼんやりの時期のことは書きようがないからである。 だからといって、被爆者はウソをいっているのではない。逆に記憶のない期間に「自分が受けたと考える以上の被害を受けた」可能性があるのである。
被爆者の記憶の中で、例外なくはっきりしているのは「どこで、何をしているときに原爆が炸裂したか」である。このことは、被災するまで「記憶の障害」をもっていなかった証左でもある。記憶の障害が出るのは被災後のことについてなのである。何が記憶をフリーズさせ、あるいは入力拒否させるのかは、人によって異なるが、入市被爆者にもおこっている点から見て、同心円を描かないと考えられる。
事例から判断するに、現存在(自分と自分の生きる世界)の急速な崩壊や大量の異形の死体との対面という「非日常」な世界への「投げこまれ」が引き金になっているように思える。「記憶がない・ぼんやりしている」ということは、脳の記憶装置に何も残っていないことを意味しない。何かのきっかけで「残っている」ものを思い出す可能性があるのである。思い出さない場合には「おぼえている(恐怖の)体験」を一層深く刻みつける。これらは後に恐怖の「引き戻らされ現象(フラッシュバック)」の土台になるのである。
感情麻痺にも同じことがいえる。「助けを求められてもこたえられなかった」「水、水といわれてもあげられなかった」「モノを扱うように死体を扱った」「荼毘に付しながら涙ひとつ出なかった」と悔恨をこめて被爆者が語るのは、あとになってからである。そのときには、感情や感性は閉ざされていた、あるいは厚いバリアが張られていたのである。そのように自我防衛機能が作動したのである。極限的状況での作業は、それなくしてはできなかったのである。
「人間的な行動を取ることさえ許されなかった状況」にもかかわらず、被爆者はその後、激しい自責の念にとらわれ、贖罪の方法を模索している。そればかりか「生き方」を規定してしまっている。「見捨てた人の死の上に、自分の生がある」(生きていることへの罪の意識)と考えている。
いまも変化しながら続く「あの日」の記憶再現
つらい記憶は毎日を生きていくために棚上げせざるを得ない。そうしなければ生きていけないのである。そうしてふつうの「心の傷」は癒えていくものである。しかし、その辛い体験につながるようなことがおきると、あっという間に「辛い体験」が恐怖とともによみがえる。だから、「つながるようなこと」がおきない生き方を選ぶようになる。そうやってもしばらくは「悪夢」や不眠に悩まされる。この一連のプロセスがPTSD(心的外傷後ストレス障害)といわれている。
被爆者もこれと同じプロセスを歩んでいる。その第一歩は「しゃべらないこと」である。いろいろ聞かれてもこたえない人、一定のこと以上は語らない人が出てくるのである。
しかし、被爆者の場合、定義されたPTSD概念では収まりきらないものをもっている。概念からはみ出てしまうというべきか。次の観点からPTSD概念の方を再定義し直す必要がある。
ひとつめは、外傷記憶があまりに強烈なので、棚上げしていても、ちょっとした刺激(閃光や雷鳴や肉の焼けるにおいなど)で記憶が再現して、一瞬にして被爆当日に連れ戻らされてしまい、それは六〇年経ったいまでも続いているという点である。六〇年後の調査でも、そんな現象をいまでもおこす可能性のある人は、少なくとも三割いる。被爆時に一六歳以下だった人のうち、爆心地に近いところで被爆した人では四〇パーセントを超えている。
ふたつめは、なるべく「思い出さない生活」を選んでも、思い出さざるを得ない事態が次々と被爆者を襲って来るという点である。まず、「差別・偏見」による。「ピカドンの子」として学校で、遊び仲間からはじかれ、縁談を断わられ、という体験をしている人は多い。次に同じ被爆者仲間が原爆症(白血病や癌など)で死んでいく。それを知るごとに、否応なしに「あの日」に自分が「連れ戻らされて」しまうのである。また、自分が病んだときに、(原爆症であろうとなかろうと)今度死ぬのは自分だと思ってしまう。このことが「引き戻らされ体験(フラッシュバック)の頻度としては一番多いと考えられる。そのたびに「心の傷」はかさぶたを引きはがされ、もっと深い傷となっていくのである。被爆者の「心の被害」といった場合、その中核となるのはこの点である。「被爆した日」が最大で、しだいに軽くなっていくのではなく、「あの日」がスタートで、軽くなるのではなく螺旋状に、次第に強くなってくるのである。なぜなのであろうか?
それは原爆被害の本質が「放射能被害」であるからである。衝撃波、爆風、熱線と一緒になって、放射能は当日も多くの人を殺傷した。爆風や熱線はいかに激しかろうと一過性のものである。しかし、放射能はあとになるほど、その悪魔性を発揮してくるのである。生き残った人に、次々と放射能による後障害が押し寄せてくる。どこまでいっても「放射能」が追いかけてくるので「心の被害」も癒えようがないのである。
さらにフラッシュバックは繰り返しているうちに微妙に変化してくる。はじめは「あの日、一瞬にして消えたまち、幽鬼のごとき被災者、大量の異形の死体」が主であり、そこにはさまって「自分が助けることができなかった」個人的なエピソードが加わる。そのうちに感情麻痺から発した「自分が生きていることの罪」強くなると、フラッシュバックをおこすたびに「助けることのできなかった」個人的なできごとの比重が増してくるのである。「自分の生」が死者の上にあるといった場合、その死者は「肉親」や「見捨てた不特定多数」よりも偶然出会った「特定された個人」である必要はどこにあるのであろうか。贖罪のためには、具体的な個人が中心に座っていたほうが自分を納得させられるとも考えられるし、人間の崇高さの発現とも考えられる。
生き残ったことの意味を問う
意識しているか否かにかかわらず、いま病んでいるかどうかにかかわらず、被爆者が今当面しているのは「生きていることの罪」意識ではなく、「ここまで生き残ったことの意味」であるように思える。もっと率直にいえば「なぜここまで生き残らされたのか」である。
一九八六年のチェルノブイリの原発事故以後、語りはじめる人、自分史を書いたり、出版したりする人が増えてきた印象をもっている。ところがここへきて、原爆症認定訴訟をおこす人がにわかに増えてきている。被爆体験を語りだす人、被爆者運動のトップに躍り出る人、新たに加わる人も出てきている。何かをせねば・・・と無意識がささやくのであろう。それは多分、サイレント・マジョリティにも同じであろう。その「なにか」が見つからなかったとしたら、それが、最後にきた「心の被害」といえるかも知れない。被爆者の戦後生活は、ままならないことの連続である。それはそのまま心気症や「軽うつ病」の温床である。「なにか」が見つからない場合心気症などに悩みながら生涯を終えることになる。原爆「被害者」のまま終わらせたくない、被害者であるからこそできる「貢献」がある。それで生きていた意味を得心してほしい――とつい力みたくなるのはわたしだけではないと思う。
結論
心の被害の土台は「あの日」に受けたトラウマである。しかし現在、「心の被害」の中核にあるのは、史上最悪の外傷記憶によるPTSDである。しかも、フラッシュバックをおこすキッカケがずっと続いているという最悪のものである。「続く」のは、原爆被害の中核が放射能被害だからである。放射能による後障害やその恐れが、次々と、新たなる心的外傷を形成するからである。「放射能が一生追いかけてくる」のである。そこに原子爆弾の悪魔性がある。
考察と主張
「心の傷」については従来、被爆者の感じ方、考え方、生き方の問題として、先人たちが明らかにしてきている。そして何よりも、被爆者自身が語り、書き、調査しまとめている。感情麻痺や「見捨て体験」から生ずる罪悪感・自責感などは被爆者ならだれでも口にする。「いわれなき差別偏見」「生きていること自体」の罪意識も同様である。リフトンはそれらを体系化し「死の呪縛」「罪の同心円」「精神的麻痺」というカテゴリーを立てている。石田は、被爆者は原爆に対する「漂流」と「抵抗」という、相反する生き方を止揚して反原爆の思想形成にいたるとしている。本書では、これらの別の枠のなかで述べられた心の傷を、当然の前提として使っている。その意味で新しい「心の傷」をたくさん見つけてはいない。それよりも、だれでもわかるように、「心の傷」の立体的構造を明らかにし、あわせてその構造の時間的変化を追った。それによって六二年たってもなお癒えず、被爆者を苦しめている「心の被害」に対する一般の理解を得られれば幸いである。
昨今、災害はもちろん、ちょっとした猟奇事件がおこるや「心のケア」が叫ばれ、ただちにしかるべきスタッフが現地に送りこまれる。これらの報道を見るにつけ、被爆者と何というちがいだろう・・・・・と思う。本来は被爆者の「心の傷」も治療・補償の対象になっていいのである。被爆者はそれを主張すべきだし、国は「心の被害」の治療・補償にいまからでも努力すべきである。国民もまたそれを支援すべきと考える。
*中澤正夫著「ヒバクシャの心の傷を追って」(岩波書店 2007.7)より抜粋